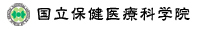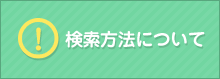病気の解説「1」での検索結果

概日リズム睡眠障害(がいじつりずむすいみんしょうがい)- 厚生労働省 (e-ヘルスネット) -
/ circadian rhythm sleep disorder /体内時計の周期を外界の24時間周期に適切に同調させることができないために生じる睡眠の障害。睡眠・覚醒リズムは、体温などの自律神経系、内分泌ホルモン系、免疫・代謝系などと同様に、体内時計によって約1日のリズムに調節されており、このような約1日の周期をもつリズムのことを概日リズムと呼んでいます。ヒトの体内時計の周期は約25時間であることがわかっていますが、地球の1日の周期は24時間であり、体内時計とは約1時間のずれがあります。日常生活において、さまざまな刺激(同調因子)を受けることにより、体内時計が外界の周期に同調して約1時間のずれが修正されています。もっとも強力な同調因子は光であり、食事や運動、仕事や学校などの社会的な因子も同調因子として働いていると考えられています。この体内時計の周期と地球の24時間の周期との間のずれを修正することができない状態が続くと、望ましい時刻に入眠し、覚醒することができなくなってきます。また、無理に外界の時刻に合わせて覚醒しても、眠気や頭痛・倦怠感・食欲不振などの身体的な不調が現れてきます。このように体内時計の周期を外界の24時間周期に適切に同調させることができないために生じる睡眠の障害を概日リズム睡眠障害といいます。概日リズム睡眠障害は、人為的・社会的な理由により体内時計を短期間にずらさなければならない場合に起こる時差症候群(時差ぼけ)、および交代勤務睡眠障害、体内時計が外界の周期に同調する機能に問題がある場合に起こる内因性概日リズム睡眠障害(睡眠相後退症候群、睡眠相前進症候群、非24時間睡眠覚醒症候群、および不規則型睡眠覚醒パターン)に分類されます。

糖尿病の新しい診断基準を7月に施行 日本糖尿病学会- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2010年05月31日糖尿病の新しい診断基準を7月に施行 日本糖尿病学会キーワード:糖尿病 糖尿病の新しい診断基準の概要が、5月27日〜29日に岡山で開催された「第53回日本糖尿病学会年次学術集会」で発表された。今回の診断基準の改訂は、前回の改訂から11年ぶりとなる。新基準は7月1日に施行される。トピック一覧へカフェイン入り「エナジードリンク」の飲み過ぎで健康障害 死亡例もがんリスクは糖尿病予備群で上昇 がん予防のためにも糖尿病予防

難病情報センター難治性膵疾患に関する研究班報告書- 難病情報センター -
HOME >> 難治性疾患研究班情報(研究奨励分野) >> 難治性膵疾患に関する研究班報告書 難治性膵疾患に関する研究班報告書 難治性膵疾患に関する調査研究 平成20年度 総括・分担研究報告書 厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患克服研究事業 難治性膵疾患に関する研究班 平成21年3月 当該報告書全334ページを章ごとにいくつかのPDFファイルにわけ、目次に従って掲載しています。 目次、構成員名簿、総括研究報告 急性膵炎1)共同研究プロジェクト 急性膵炎2)各個研究プロジェクト 慢性膵炎1)共同研究プロジェクト 慢性膵炎2)各個研究プロジェクト 自己免疫性膵炎1)共同研究プロジェクト 自己免疫性膵炎2)各個研究プロジェクト 膵嚢胞線維症1)共同研究プロジェクト、2)各個研究プロジェクト 研究成果の刊行に関する一覧表、資料、参考 一括ダウンロード 項目 PDF

WPW症候群による突然死のリスクとアブレーションのリスク- 日本心臓財団 -
息子のことでご相談します。小学校入学時の健康診断で心電図検査の結果、WPW症候群との連絡を受け、病院で精査した結果、やはりWPW症候群と診断されました。自覚症状は、年に4?5回、心臓がドキドキすることがありますが、数分で治まります。運動をしたからっといってなるわけではありません。遊んでいるときや普通に授業を受けているときに突然起こります。症状が軽いことから、年1回の検査だけで経過観察中です。しかし、突然死の原因にもなるようですし、運動クラブでの活動など、激しい運動も続けていきたいので、カテーテルアブレーションを行なって完治させたいとも考えています。激しい運動を続けながらの生活で、突然死を起こす確率と、カテーテルアブレーションを行なって失敗(死亡または重度の後遺症)する確率はどちらが高いのでしょうか。1)WPW症候群で突然死する頻度は古い時代のものしかありませんが、0.01ないし0.03%、つまり、1万人に1ないし3人という頻度といわれていました。ただ、今日では、突然死する場合の電気生理学的特徴がわかってきていているので、検査をすることにより、ある程度は予測することができるようになっています。2)カテーテルアブレーションでも死亡事故が起こる可能性はありますが、近年では、死亡例の報告はありません。しかし、房室ブロック、一過性脳虚血、大動脈弁閉鎖不全などといった事故についていえば、0.5ないし0.7%、つまり、1,000人中、5ないし7人に起こるといわれています。

心房細動の治療- 日本心臓財団 -
1年半前、心房細動による不整脈との診断を受け、主治医から「今の医学では処置方法がないので、今のままこの薬を服用しながら処置法が見つかり次第、行ってみましょう」と言われています。私は、サイクリングを好んでしていますが、治せるものならば早く治して、気がね無しに運動したいです。先生には運動をしても良いと言われたのですが、心配です。1)治せる方法は無いのですか?2)運動は、どのくらいまでなら良いのでしょうか?1)心房細動をもとの洞調律(正常のリズム)にもどす治療には2つの方法があります。薬を用いる方法と電気ショックによる方法です。これまでアスペノン以外にいろいろな薬を試みているのだろうと思いますが、いずれにせよ既に1年半が経ち正常のリズムに戻ることなく慢性化しているものと判断されます。慢性化してしまっているから正常のリズムに戻すのは無理だろうと考えて心房細動のままにしておくこともよくあります(ことに高齢者の場合)が、そういう場合には日常生活に支障がない程度に心拍数を抑える薬を服用する必要があります。治せるものなら何とか治したいと考える場合には電気ショックを試みることになります。長時間心房細動が持続した場合にはもとに戻らないだろうと考える医師も多いようですが、1年半ぐらいなら治る可能性はあります。まだ36歳という若さだし一度試みてもよいのではないかと思います。大きな病院の循環器科を受診して相談されてみてはいかがでしょうか。2)可能な運動の程度を知るには2つの方法があります。ひとつはトレッドミル試験です。心拍数と心電図を記録しながら、運動して、適切な運動の範囲を調べます。二つ目は携帯型心電計を装着した状態で、運動をして、どこまでなら大丈夫かを調べます。いずれにしても、担当医にご相談ください。

スポーツ心臓で房室ブロックといわれた- 日本心臓財団 -
主人が先日、機会があって心電図検査を受けたところ、1度房室ブロックとの結果でした。先生のお話では、スポーツ心臓で問題ないとのことでした。本人は、高校から大学(現在も在学中)までラグビーをしています。ラグビーの練習は週に2回くらいです。他に週2回ほど、ジムへ行って筋トレなどで体を鍛えたりしていますが、スポーツ選手のように激しいトレーニングを毎日行っているわけではありません。ラグビーは激しいスポーツだし、きちんとトレーニングを積んでいないから、余計に心臓に負担がかかるということでしょうか?検査前までは特に自覚症状はなかったようですが、結果が出てから思い返してみると、ラグビーで夢中になって走っている最中に、心臓が太鼓をうっているように激しく拍動しているのを感じたり、脈を自分ではかったときに乱れるのを感じることがあった、とのことです。他に、普段から自分の脈拍や心臓の鼓動を強く感じている(拍動に合わせて、手に持っている新聞などが動くことがある)といいます。それは、血圧が高めな(上が140くらい)せいでしょうか?先生は、1度の房室ブロックで、若い人にはよくあるスポーツ心臓だから心配いらない、とのことですが、1度の房室ブロックには、トレーニングをやめて数年かけて正常にもどるものもあるし、2度3度へと移行するものもあると本で読み、心配しています。1)スポーツ選手ほどの運動をしていなくても、スポーツ心臓になるのでしょうか2)少しの自覚症状はあるけれど、スポーツを続けても大丈夫でしょうか3)悪化していく可能性があるのでしょうか4)悪化させないためには、トレーニングなどをやめたほうがいいのでしょうか。1)スポーツ選手ほどの運動をしていなくても、スポーツ心臓になるかというご質問ですが、ご主人の運動ぶりは普通の人以上のようであり、スポーツ心臓になっても不思議ではありません。2)すこしの自覚症状があるといいますが、その症状はブロックが強まったための症状ではありません。ブロックとは関係のない症状のようです。3)悪化するとは、ブロックが進行して、完全房室ブロックになる可能性があるかということでしょうか。それはないとはいえないでしょうが、経験されることではありません。4)悪化させないために、運動を止めるということですが、それよりも、運動をつづけて、万が一、悪化すれば、そのときに運動を止めるという考え方の方が現実的ではないでしょうか。そうはならないと思いますし、それに、進行して、完全ブロックになってから運動を止めても、間に合わないというような事態にはならないはずです。

小学生でアブレーション治療は可能か- 日本心臓財団 -
小学校6年生の娘が、2年ほど前にWPW症候群及び発作性頻脈と診察されました。しばらく自覚症状は何もなかったのですが、ここ1年ほど前から、頻脈発作が起こり、5分程度で治まるという症状が1ヶ月に1度くらい発生していました。しかし、先日クラブ活動中に初めて25分間という長い発作があったことから、娘は中学生になって十分な運動クラブ活動ができるように、小学生のうちに手術を受けて根治したいと言い出しました。1)小学校6年生で、アブレーション手術は可能でしょうか。2)発作性頻脈はホルモンバランスと関係があると聞いたことがあります。ホルモンバランスが落ち着いた頃(高校生や大学生)を待って手術したほうがいいでしょうか。3)手術後、将来的に手術の後遺症の危険性はゼロでしょうか。4)WPW(発作性頻脈)は、たとえば突然死というようなことの原因になる可能性はないのでしょうか。1)小学校6年生であれば、十分にアブレーション治療が可能です。2)頻拍発作自体は思春期というホルモンバランスの影響を受ける可能性はありますが、アブレーション治療の効果が影響を受けることはありません。3)治療の後遺症が長い期間を経て出てくるということがあるのか、についてはまだ、データがありません。しかし、後遺症がかなりな年数を経て起こってくるということはないであろうと思います。4)きわめてまれに、突然死の原因になるWPW症候群があります。しかし、それは事前の検査でわかります。担当医におたずねになってください。

肥満と房室ブロック- 日本心臓財団 -
健康診断の心電図検査で、第2度房室ブロック(モビッツ2型)と言われました。医師の話では、年齢を考えるとペースメーカはまだ早いと思うが、たまたま取った健康診断の心電図に顕れるということはかなりの頻度で房室が止まっているとも思えるので、今のところ何とも言えないとのことでした。心電図再検査は異常がなく、今後、24時間ホルター心電図検査と超音波検査を行います。昨年冬頃から、時々めまいを感じていました。また、ここ10年で、体重が50キロ前後から87キロに増えました。急激に太ったことが病因なのでしょうか。痩せれば治るのでしょうか。他のサイトで「突然死の可能性あり」とありましたが、本当ですか。めまいがあるときに、ブロックが起こっていたり、あるいは2個以上の心室興奮が脱落しているのであれば、ブロックに対して、ペースメーカを入れることをお勧めします。モビッツ2型といっても、1個だけの心室興奮の脱落であれば、モビッツ1型との区別はできません。次第に伝導性が低下するという時期がたまたま捉えられなかったというだけの可能性があるからです。ご存じのように、モビッツ1型は良性で、めまいなどの原因にはなりません。これを確かめていただいてください。肥ると肥満症候群あるいは睡眠時無呼吸症候群などといって、迷走神経緊張が高まってくる時期があり、モビッツ1型のブロックが起こりやすくなります。これならば、やせれば治ります。肥満があるという点からも、あなたさまのブロックはモビッツ1型ではないかと思われます。ブロックの際の、心室興奮の脱落が長く続けば、突然死の危険があります。

房室ブロックとかWPW症候群といわれたりする- 日本心臓財団 -
15歳の息子のことで教えてください。昨年、学校の定期検診で房室ブロック1度のため、再検査するように言われ、総合病院を受診したところ、WPW症候群と診断されました。主治医は、今まで自覚症状もないし、日常生活に支障もないし、運動制限はないけれど、年1回程度、心電図をとって経過観察しましょうと言われました。1)学校の検診では房室ブロック1度と言われながら、再検ではWPW症候群と診断されました。別の病院でもう一度検査したほうがよいでしょうか。2)WPW症候群の診断を受け、運動制限がないと言う診断書を提示しても、運動部を継続したいのであれば、保護者として何が起きても責任を問わないと言う誓約書の提出を求められました。WPW症候群というのは、それほど気を使わなければならないものなのでしょうか。1)房室ブロックとWPW症候群とは別のものです。病院では循環器科を受診なさったのであれば、病院の診断が正しいと思います。学校検診では担当医は必ずしも循環器科の専門医ではないからです。したがって、病院での医師の指示に従うのがよいと思います。2)WPW症候群では7割の人には何も起こらないのですが、3割くらいの人では、頻脈発作を起こすことがあります。これ自体は危険ではないのですが、頻脈発作が起こっている状態で、全力疾走をつづけるなどすれば、倒れてしまいます。運動は何をしてもよいのですが、具合が悪くなったら、休ませてもらうことが大事でしょう。

上室頻拍のカテーテル治療- 日本心臓財団 -
10年ほど前に発作が1、2日置きに出るといったことが2ヶ月くらい続いたこともありましたが、それ以降発作頻度は減り、1ヶ月に1度起きるか起きないか といった状態でした。ところが昨年から発作が頻発するようになり、調子の悪いときで週に2度、少しよくなっても2、3週間に1度という状態です。発作が起きなくてもドックン(強く打つ)となったり、ドクドク(2、3拍だけ早い)といったこともよくあります。発作時はワソランを2錠、発作が起こりそうな時には1錠を服用しています。現在はいつ発作が起きるかと不安を感じながらも、会社に普通に行っております。担当の先生に相談しましたところ、「発作が頻発するようであれば、入院して焼灼術治療(カテーテルアブレーション)するのがよい」とおっしゃいます。治療方法をご説明いただいたところ、カテーテルを刺すところのみ局部麻酔で、4時間くらいを要して行われるとのことでした。お聞きしただけでもとても怖くなり、その治療をお願いする決心がつきません。やはりカテーテル治療をしたほうがよいのでしょうか。発作がどれくらい頻繁にあるかが問題ですが、その時の症状や、従来の経験などから方針を決めることになるでしょう。焼灼法は最近多く行なわれるようになったもので、小さい領域の操作ですので、危険は少ないと思います。ただしケースにより100%成功するとは限りませんので、主治医とよくご相談ください。症状が強く、薬で予防や治療が困難の時は焼灼法を試みてもいいでしょう。あるいはもう少し薬などで経過をみるという手もあり得ます(自然に減少する例もあります)。

房室ブロック2度- 日本心臓財団 -
27歳の夫の房室ブロック2度について相談します。年に一度のホルター心電図検査では、昨年と変化はなく、寝ている時や、安静にしている時に脈が飛ぶようですが、本人には自覚症状がないそうです。主治医には、今後、ペースメーカを入れることになるかもしれないけれど、個人差があるので、どうなるかはまだ分からないと言われているそうです。1)どのくらいの確率でペースメーカを入れる必要があるのでしょうか?2)ペースメーカを入れたときのリスクはありますか?3)この病気が違う心臓病の原因になりうるのでしょうか?房室ブロック2度というのはときに脈が脱落することがある房室ブロックです。これには、1型と2型とがあります。1型は若い人、運動選手によくみられるもので、何ら処置することなく、放置していて差支えない場合であり、2型は警戒を要する場合です。2型の場合には、ときにめまいとか失神発作などといった症状がみられます。まだ若いので、年に一回、24時間ホルター心電図検査を受けているという程度のことですから、多分、1型の良性の房室ブロックなのでしょう。絶対に大丈夫と言い切るわけにもいかないので、毎年、チェックしているものと思います。1)ペースメーカをつけることになる確率は、まず、0に近いであろうと思います。2)ペースメーカをつけたときのリスクは、ほとんどないといってよいのですが、強いていえば、ペースメーカが身体に合わないためのペースメーカ症候群という状態があります。3)房室ブロックのために別の異なる心臓病が起こってくるというようなことはありません。あまり気になさらないでよいのではないでしょうか。

心房中隔欠損は自然封鎖するか- 日本心臓財団 -
1ヶ月検診時に、心雑音があるとのことでエコー検査を実施したところ、心房中隔欠損があるとの診断で、あと4ヶ月程様子を見ましょうと言われました。現在の穴の程度は小さいし、自然に塞がるケースもあるからとのことでした。また、とりあえず、通常の生活を送っていても大丈夫と言われました。1)心房中隔欠損は先天性の奇型で、遺伝によるものなのでしょうか。2)自然に塞がるケースもあるのでしょうか?また、逆に大きくなることはないのでしょうか。3)異常が進行した場合、何か兆候があるのでしょうか。4)塞がらない場合、手術をすることになるのでしょうか。5)手術の場合、1歳未満で実施して大丈夫なものでしょうか。1)心房中隔欠損は心房に穴があいている先天性奇形ですが、元々胎児では心房に卵円口と呼ぶ穴があり、生後に閉じます。この穴が異常に大きいのも、心房中隔欠損です。遺伝性はほとんどありません。2)小さい穴は自然に塞がります。大きくなることはあまりありません。3)進行するのは大人になってからです。進行すると、不整脈、心不全を生じます。4)直径10ミリ以下の小さい穴は手術しません。5)手術をする年齢は2?3才以上です。1才以内に急ぐのは、肺高血圧と心不全を合併する場合だけです。

発作性上室頻拍発作による不安と吐き気- 日本心臓財団 -
初めての頻脈発作は24歳の時でした。頻度は年に3?4回ほどでしたが、現在は月に2?5回です。医師からは、発作性上室頻拍と診断され、頻度が多くなったらアブレーション治療を考えるけれど、抗リン脂質抗体症候群があるので、リスクがあると言われています。発作は床に落ちたごみを拾ったり、子供を下から抱き上げたりする時によくなります。発作が起きたときはすぐに仰向きで寝て深呼吸を2?3回すると治まることが多いです。冷水を飲んでも息を止めても治まりません。最近は発作が始まって脈を測っていると不安感がおそってきて、脈がどんどん速くなり、すごく不安になります。1)アブレーションは抗リン脂質抗体症候群だとやはりリスクが大きいでしょうか。2)月2?5回の発作は多いほうですか。3)発作性上室頻拍で死ぬことはないのでしょうか。4)発作時に薬を飲むのが不安で、1度もワソランを飲んだことがありません。やはり発作がおきたら飲んだほうが良いのでしょうか。5)この病気は若い人に多い病気とききました。年老いたら治ることはありますか。それとも一生付き合っていかなければいけないのでしょうか。6)不安感が大きいときの発作と比較的小さいときの発作がありますが、自律神経に関係ありますか。また不安感が大きいときは脈もどんどん速くなり、嘔吐してしまうこともあります。この症状も発作性上室頻拍だからでしょうか。7)1回発作が起きるとその日のうちにまた発作が起きることがありますが、1回起きると続きやすいのですか。1)抗リン脂質抗体症候群では血栓形成が起こりやすいとされています。アブレーション治療をすると、必ず血栓ができるというわけではないので、この症候群があるときに、アブレーションをすると血栓ができやすいという報告は見あたりません。しかし、注意しなければならないことには間違いないであろうと思います。2)月に2回までなら多くはありませんが、5回となると多いように思います。3)上室頻拍発作で死ぬことはありません。4)深呼吸を2ないし3回すると治るということですので、薬の必要はないのではないでしょうか。5)誰でもというわけではありませんが、年とったら、発作は起こらなくなるということはあります。6)自律神経は発作に深い関係があります。発作のときに、吐くことがありますが、吐くことで、発作が停止することはしばしば経験されています。7)度々起こると、つづけて起こることはあります。起こった後はしばらく安静にしていることが大事です。8)服薬はいつもというのではなくて、発作が起こったときにだけ服用することが勧められています。このためにはいつも、ポケットに薬を忍ばせておく必要があります。

アペルト症候群とファロー四徴症- 日本心臓財団 -
ファロー四徴症とアペルト症候群があり、ファロー四徴症については、2歳くらいに、10Kgを超えたころを目安にして手術をするとのことです。今年の春、1歳1ヶ月目に頭蓋骨縫合早期癒合症の拡張術を受けました。ファロー四徴症をもっているため、手術後、2日目にSPO2が50台?60台をいったり来たりしています。術後の痛みのためか、時折痛がる時には、40台前半になることもあります(インデラル服薬中)。手術自体が、脳外科担当でありSPO2の値に対して、説明はありません。(術後なので、多少落ちることもあるとの説明でした。)循環器の先生には、術後SPO2が落ちることもあると言われてはいましたが、このような状態で大丈夫なのかどうかがわからず、非常に心配です。SPO2の適正値、脳への影響等について教えてください。1歳1月でApert症候群でファロー四徴症のお子さんです。頭蓋骨の拡張手術後に低酸素が進んでSPO2が50%台になるのが心配です。SPO2の値は貧血が無い場合は70?60%でも大丈夫でしょう。50%台ではチアノーゼ発作が心配です。チアノーゼ発作を起こさない予防法には、輸血でヘモグロビンを多くしておくこと、インデラルなどのベーターブロッカーの薬を飲むことをまずします。今までチアノーゼ発作が起こってないようですが、チアノーゼ発作が起こらない場合は脳への後遺症は生じません。

児童の心室性期外収縮- 日本心臓財団 -
小学校1年生の一斉心臓検査で「心室性期外収縮」と診断されました。今年、2年生の検診でも同様の診断結果でした。生まれてから小学校に入るまで、心臓疾患の指摘はありません。以下の点について気にかかります。ご指導ください。1)出産時の胎児の心拍が数回停止していましたが、関係ありますか。2)小学校経由でもらった診断結果には、「運動制限の必要なし」とありましたが、山登り(ハイキング程度)、飛行機による海外等への移動は、気にしなくて大丈夫ですか。3)小学校1年、2年の検診で耳鼻科でも引っかかり、「鼻炎」と「扁桃腺肥大」と診断されましたが、呼吸器系と循環器系の因果関係はあるのでしょうか。4)子どもが寝ているときに、背中に耳を当てて鼓動を聞くと、確かに脈が乱れています。(20?30回に1度の割合で乱れる場合と、10回にならない間に乱れる場合とまちまちです。一度、大学病院で見てもらったほうがよいでしょうか。1)心室期外収縮は健康な人にもしばしばみられます。胎児のときの不整脈とは関係がありません。2)基礎に心臓疾患がなく、不整脈の心電図波形に問題がないときには、心配なしと判断されるのが通例です。運動制限の必要なしとあれば、大丈夫です。3)呼吸器疾患と循環器疾患とは直接の関係はありませんが、扁桃腺肥大が著明で、息苦しい状態があると、不整脈は起こりやすくなります。4)大学病院にいく必要があれば、指示が出るはずです。心配なさることはないでしょう

難病情報センター患者団体50音順一覧 (JPA加盟団体を除く)- 難病情報センター -
1p36欠失症候群家族会 〒162-8666 東京都新宿区河田町8-1 東京女子医科大学統合医科学研究所内 TEL:03-3353-8112 内線24013 一般社団法人 東京進行性筋萎縮症協会 とうきんきょう 〒132-0035 東京都江戸川区平井5-19-1 TEL/FAX:03-3614-0225 一般社団法人 日本筋ジストロフィー協会 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-43-11 福祉財団ビル TEL:03-6907-3521/FAX:03-6907-3529 一般社団法人 日本網膜色素変性症協会(JRPS) 〒140-0013 東京都品川区南大井2-7-9 アミューズKビル4F

難病情報センター高チロシン血症2型(指定難病242)- 難病情報センター -
HOME >> 診断・治療指針(医療従事者向け) >> 高チロシン血症2型(指定難病242) 高チロシン血症2型(指定難病242) こうちろしんけっしょう2がた 病気の解説(一般利用者向け) 診断・治療指針(医療従事者向け) FAQ(よくある質問と回答) 告示病名以外の指定難病対象疾病名はこちらにあります。 (概要、臨床調査個人票の一覧は、こちらにあります。) ※こちらの内容は以下の難病共通になります。 高チロシン血症1型(指定難病241) 高チロシン血症2型(指定難病242) 高チロシン血症3型(指定難病243) ○ 概要 1. 概要 チロシンはチロシンアミノ基転移酵素によって4-ヒドロキシフェニルピルビン酸、続いて4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素によってホモゲンチジン酸、ホモゲンチジン酸酸化酵素によってマレイルアセト酢酸、マレイルアセト酢酸イソメラーゼによってフマリルアセト酢酸、フマリルアセト酢酸分解酵素によってフマル酸とアセト酢酸に分解される。高チロシン血症には種々の原因があり、1型、2型、3型の3つの病型に分類されている。これらの疾患は、遺伝的・酵素学的に別の疾患であり、臨床症状出現の機序も異なる。遺伝形式はいずれ

難病情報センター高チロシン血症3型(指定難病243)- 難病情報センター -
HOME >> 診断・治療指針(医療従事者向け) >> 高チロシン血症3型(指定難病243) 高チロシン血症3型(指定難病243) こうちろしんけっしょう3がた 病気の解説(一般利用者向け) 診断・治療指針(医療従事者向け) FAQ(よくある質問と回答) 告示病名以外の指定難病対象疾病名はこちらにあります。 (概要、臨床調査個人票の一覧は、こちらにあります。) ※こちらの内容は以下の難病共通になります。 高チロシン血症1型(指定難病241) 高チロシン血症2型(指定難病242) 高チロシン血症3型(指定難病243) ○ 概要 1. 概要 チロシンはチロシンアミノ基転移酵素によって4-ヒドロキシフェニルピルビン酸、続いて4-ヒドロキシフェニルピルビン酸酸化酵素によってホモゲンチジン酸、ホモゲンチジン酸酸化酵素によってマレイルアセト酢酸、マレイルアセト酢酸イソメラーゼによってフマリルアセト酢酸、フマリルアセト酢酸分解酵素によってフマル酸とアセト酢酸に分解される。高チロシン血症には種々の原因があり、1型、2型、3型の3つの病型に分類されている。これらの疾患は、遺伝的・酵素学的に別の疾患であり、臨床症状出現の機序も異なる。遺伝形式はいずれ

薬ののみ方、使い方- 国立がん研究センター -
HOME > 診断・治療 > くすりの使い方と注意点 > 薬ののみ方、使い方 薬ののみ方、使い方 更新日:2006年05月18日 [ 更新履歴 ] 更新履歴 2006年05月18日 更新しました。 2003年05月13日 掲載しました。 閉じる 1.薬ののみ方について 2.薬をのむタイミング 3.とんぷく薬(頓服薬)ののみ方 4.薬は慌てず余裕を持って(包装の誤飲) 5.坐薬の使い方 6.点眼薬の使い方 7.眼軟膏の使い方 8.腟坐薬、腟錠の使い方 9.点鼻薬の使い方 10.点耳薬の使い方 11.うがい薬の使い方 12.湿布薬(パップ剤)の使い方 13.ハンドネブライザー(吸入用エアロゾル)の使い方 14.ハンドネブライザー(吸入用エアロゾル)の種類 1.薬ののみ方

難病情報センターその他腎性低尿酸血症(平成23年度)- 難病情報センター -
HOME >> 難治性疾患研究班情報(研究奨励分野) >> 腎性低尿酸血症(平成23年度) その他腎性低尿酸血症(平成23年度) じんせいていにょうさんけっしょう 研究班名簿 一覧へ戻る 1. 概要 腎性低尿酸血症は、腎臓における尿酸の再吸収低下または分泌亢進といった尿酸の排泄亢進に起因する尿酸輸送体病であり、血清尿酸値の低下と尿中尿酸排泄率の増加を特徴とする。合併症として重篤な運動後急性腎不全や尿路結石が問題