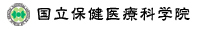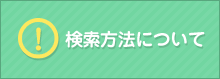病気の解説「脳卒中」での検索結果

糖尿病の人は循環器疾患やがんによる死亡率が高い 9万人を調査- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2015年09月04日糖尿病の人は循環器疾患やがんによる死亡率が高い 9万人を調査キーワード:糖尿病 糖尿病の人はそうでない人に比べ、心筋梗塞や脳卒中などの循環器疾患やがんによる死亡率が上昇することが、国立国際医療研究センターなどの研究グループが実施している、日本人9万人を対象とした多目的コホート研究「JPHC研究」で明らかになった。糖尿病の人では死亡リスクが増加 「JPHC研究」はさまざまな生活習慣と、がん・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。今回の研究では、40~69歳の男女約9万人を対象に1990年または1993年から2011年まで追跡調査した。 研究グループは、1990年と1993年に岩手、秋田、長野、沖縄、東京、茨城、新潟、高知、長崎、大阪の11保健所管内に在住しており、がんや循環器疾患になっていなかった40~69歳の男女約10万人を、2010年末まで追跡し調査した。結果にもとづき、糖尿病(自己申告)の有無と全死亡・主要死因死亡との関連を調べた。 糖尿病は一般的には生命に関わる疾患とは考えられていない傾向があるが、糖尿病の人ではそうでない人と比べて死亡のリスクが高いという研究報告がある。研究グループは日本人において、糖尿病と全死亡および循環器疾患による死亡、がんによる死亡のリスクとの関連を調べた。 その結果、研究開始時に糖尿病があった群ではそうでない群と比べて、総死亡の危険度のハザード比(95%信頼区間)は、男性で1.60倍(1.49-1.71)、女性で1.98倍(1.77-2.21)に増加していることが判明した。 死因別に解析したところ、循環器疾患による死亡については男性で1.76倍(1.53-2.02)、女性で2.49倍(2.06-3.01)、がん

牛や豚の赤肉を食べすぎると糖尿病リスクが4割上昇- 日本生活習慣病予防協会 -
(JPHC研究)魚をよく食べる男性は糖尿病リスクが低い インスリン抵抗性の改善にも期待白米をとりすぎると日本人女性で糖尿病発症のリスクが上昇緑茶、コーヒーを毎日飲むと脳卒中リスクが低下脳卒中リスク 簡単に予測できる算定表を開発 高血圧が最大要因清涼飲料水の飲み過ぎ 糖尿病と脳梗塞のリスクが上昇高カロリー飲料の飲み過ぎで脳卒中リスクが2倍に禁煙しても5年間は糖尿病に注意 6万人調査で判明 JPHC研究糖尿病と脳卒中 糖尿病は脳梗塞の発症リスクを上昇させる(Terahata)◀ 前の記事へ次の記事へ ▶ 関連トピック 疾患 ▶ 糖尿病

糖尿病(とうにょうびょう)- 厚生労働省 (e-ヘルスネット) -
インスリンの作用不足により高血糖が慢性的に続く病気。網膜症・腎症・神経障害の三大合併症をしばしば伴う。糖尿病は、インスリンというホルモンの不足や作用低下が原因で、血糖値の上昇を抑える働き(耐糖能)が低下してしまうため、高血糖が慢性的に続く病気です。重症になると血液中の糖が尿にあふれ出ることで甘い匂いがするのためその名がありますが、診断は尿糖ではなく空腹時血糖や75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験)などの血液検査によって行われます。1型糖尿病と2型糖尿病があります。1型はインスリン依存型とも呼ばれ、自己免疫疾患などが原因でインスリン分泌細胞が破壊されるもので、インスリンの自己注射が必要です。一方で2型はインスリン非依存型と呼ばれ、遺伝的要因に過食や運動不足などの生活習慣が重なって発症します。その他の特定の疾患や機序(メカニズム)によるものや妊娠糖尿病がありますが、多くは2型であり、日本ではその疑いがある人(可能性を否定できない人を含む)は成人の6人に1人、約1870万人にのぼっています。糖尿病の恐さは、自覚症状のないままに重篤な合併症が進展することで、微小な血管の障害である網膜症・腎症・神経障害の三大合併症のほか、より大きな血管の動脈硬化が進行して心臓病や脳卒中のリスクも高まります。生活習慣の改善によって糖尿病を発症する手前で防ぐ1次予防、たとえ発症してもあきらめずに血糖値を良好にコントロールして健康に生活する2次予防、さらに合併症の発症をくい止める3次予防がいずれも重要になってきます。

10万人のゲノムを長期調査 遺伝情報と生活習慣病の関連を解明- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2010年07月09日10万人のゲノムを長期調査 遺伝情報と生活習慣病の関連を解明キーワード:糖尿病 心筋梗塞/狭心症 脳梗塞/脳出血 認知症 生活習慣病の医療費 政府の総合科学技術会議(議長・菅直人首相)では、来年度予算で特に重点配分を求める科学技術の重要施策のうち、10万人の遺伝情報(ゲノム)と生活習慣との関連を調べ、脳卒中や心筋梗塞などにつながる遺伝・環境要因の解明をめざす「ゲノムコホート研究」や、病気を早期診断・治療できるようにする技術、医薬品、機器の開発を重視している。トピック一覧

第2回:こころの問題に立ち向かう- 厚生労働省 (みんなのメンタルヘルス) -
独立行政法人国立精神・神経医療研究センター 理事長 樋口 輝彦--> 第2回:こころの問題に立ち向かう 独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 社会精神保健研究部長 伊藤 弘人 ジェラルド・フォード第38代アメリカ大統領の夫人であるベティ・フォード氏が、2011年7月8日に93歳で逝去されました。夫人は自らの経験を率直に公表される方でした。ご自身のアルコール問題等での入院の経験をきっかけに、専門施設であるベティ・フォード・センターを設立するなど、依存症問題の改善に資する啓発・支援に尽力されました。 アメリカ政府要職者の夫人は、こころの問題に立ち向かう方が少なくありません。ロザリン・カーター氏(ジミー・カーター第39代大統領夫人)は、メンタル・ヘルス大統領委員会の名誉議長を務め、精神保健医療政策の推進に大きく寄与してきました。ティッパー・ゴア氏(アル・ゴア副大統領夫人)は、ホワイトハウスでメンタルヘルスの推進に注力しました。 わが国においても、こころの問題に立ち向かうことを応援する方々が、さまざまな方面で増えてきています。1年間に国民の約40人に1人がこころの問題で医療を受けていますので、10~20年で考えるとその割合はもっと高くなり、とても身近な問題となっていることも影響しているかもしれません。学術的にも、糖尿病などの生活習慣病と同じく、精神疾患を早期発見・早期治療をすると予後がよくなるという考え方が主流になりつつあります。医療にかかりやすくなることは、必要な方々の受療が進んでいるのであれば望ましいことです。 医療の中での連携も進んでいます。がん、心筋梗塞、脳卒中や糖尿病などを患うと、こころの問題が出てきて、その一部は専門的治療を受けることで軽減されることが、国際的に明らかになってきました。わが国のがん治療の中にこころを担当する専門家がチームの一員に位置づけられており、心疾患領域においてもその基盤が整備されつつあります。 さらに心強いことに、近年、当事者の方が保健医療政策の立案に参画されることが一般的になっています。ベティ・フォード氏の功績を称え哀悼の意を表するとともに、わが国においても、学術的な蓄積をベースに、当事者の観点が十分に反映されることにより、よりよい精神保健医療サービスが提供され、国民の保健医療福祉の向上につながることを願います。

難病情報センターもやもや病(指定難病22)- 難病情報センター -
の人数は、平成25年度1万6086人でした。昭和57年度に最初に599人に発行されてから32年間で徐々に増加していますが、必ずしも患者さんが増加しているわけではなく病気が広く認識され、診断される機会が多くなったものと考えられます。 3. この病気はどのような人に多いのですか もやもや病には家族内発症するかたが10〜12%程度に見られると言われています。つまり、本人がもやもや病の場合、その親や兄弟姉妹、いとこなどにももやもや病の方がいる可能性が一定程度(10−12%程度)ありうるということです。 4. この病気の原因はわかっているのですか 病気の原因はまだ解明されていません。もやもや病患者さんに病気の症状がおこるメカニズムや、ある特定の遺伝子を持つ方に発症し易い傾向があることまでは最近の研究で明らかにされています。 5. この病気は遺伝するのですか 現在わかっている範囲では、もやもや病の患者さんから生まれたお子さんが、必ずしも、もやもや病を発症するとは言い切れません。兄弟がもやもや病のかたがいらっしゃる場合に、必ずしもそのご本人がもやもや病を発症するとは言い切れません。遺伝の関わる疾患ではあるけれども、必ずしも親子や兄弟で伝わるとは言い切れないというのが現在のデータが示す事実です。 家族内発症を高頻度に起こしている家系があることが知られています。一方で、家族歴なく発症している患者さんも見られます。どの病気にも共通して言えることですが病気の成りやすさには遺伝的素因が関わっています。この素因そのものに直接脳血管を閉塞させる性質はなくてもある他の要因が加わると、脳の血管に異常を来すという性質のものなのかもしれません。 患者さんの家族の中に、比較的若くして脳卒中を患った家族がいる場合などは、家族性発症が疑われます。従って、このような患者さんに御兄弟、姉妹がいる場合は脳の血管をMRIなどで調べるのが良いと思われます。 6. この病気ではどのような症状がおきますか 前頭葉の血流不足による症状が起きやすく、症状が一時的に起こり回復する事がしばしば見られます。そのため、医療機関への受診が遅れることもあるので注意が必要です。典型的には、手足の麻痺が生じます。言葉が話せなくなったり、ろれつがまわらなくなるといった言語障害もしばしば見られます。小児には、熱いめん類などの食べ物をたべるときのふーふーと冷ます動作や、フルートなどの楽器演奏や走るなど息がきれるような運動が引き金となって症状がでることがしばしば見られます。脳内の二酸化炭素濃度が低下して脳血管が収縮しさらに血流不足になることが原因です。また脳梗塞や脳出血を発症

難病情報センター禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症(指定難病123)- 難病情報センター -
signalを調節している。そのため、TGF-beta superfamily signalの調整障害がCARASILの病態に関与している可能性が想定されている。 3.症状 遺伝子診断によって確定された13例の解析では、禿頭は平均16.7歳(0~27歳)、変形性脊椎症は平均30.4歳(21~39歳)、歩行障害は平均30.7歳(23~39歳)、初発の脳卒中は平均31.0歳(24~38歳)、認知症は35.1歳(24~50歳)で発症する。禿頭を伴わない症例も報告されており、禿頭の合併頻度は69.2%である。歩行障害と認知症は脳卒中によって悪化するが、明確な脳卒中がみられなくても緩徐進行性の経過をたどる。進行すると構音障害や嚥下障害を呈する。 4.治療法 確立された治療法はない。 5.予後 認知症と運動障害が生涯にわたって進行し、平均40歳で車椅子を使用するようになる。症状は非可逆的であり、進行期には全ての日常生活動作に介助が必要になる。生命予後についてはデータが少なく不明である。 ○ 要件の判定に必要な事項 1. 患者数 100人未満 2. 発病の機構 不明(TGF-beta superfamily signalの調節障害が病態に関与している可能性がある。) 3. 効果的な治療方法 未確立(高血圧・糖尿病の管理が必要となるが、根治的治療はない。) 4. 長期の療養 必要(進行性である。) 5. 診断基準 あり(研究班作成の診断基準あり) 6. 重症度分類 modified Rankin Scale(mRS)、食事・栄養、呼吸のそれぞれの評価スケールを用いて、いずれかが3以上を対象とする。 ○ 情報提供元 「遺伝性脳小血管病の病態機序の解明と治療法の開発班」 研究代表者 新潟大学脳研究所生命科学リソース研究センター分子神経疾患解析学分野 教授 小野寺理 <診断基準> Definite、Probableを対象とする。 禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症(CARASIL)の診断基準 1. 55歳以下の発症(大脳白質病変又は中枢神経病変に由来する臨床症候) 2. 下記のうち、2つ以上の臨床症候ないし検査所見 a. 皮質下性認知症、錐体路障害、偽性球麻痺の1つ以上 b. 禿頭(アジア系人種40歳以下) c. 変形性脊椎症又は急性腰痛

心房粗細動、アブレーション治療とは- 日本心臓財団 -
心房粗細動、アブレーション治療とは 心房細動は、心臓に病気がある人だけでなく、ストレスや不規則な生活習慣でも起きてきます。自律神経活動の亢進が誘因となりやすい不整脈として知られており、日中に起きやすい、夜間に起きやすい、食後や飲酒後に起きやすい、運動時に起きやすい、などはその典型的な場合と言えます。 心房細動は、心房の部分部分がまったくばらばらに収縮する状態、いわば心房がこきざみ震えている状態で、これに伴って心室の収縮にも規則的なリズムがなくなり、脈拍は大きさも間隔も不規則なものとなります。心房細動には時々起こる発作性のものと慢性のものとがあります。心臓弁膜症、先天性心疾患などいろいろな心臓病で見られるほか、健康な人にも起こります。最近では高齢者によく見られますが、高齢者の場合は病気というより老化現象といってよいもので、発作性に始まったものでもやがては慢性の持続的なものになってしまいます。 心房細動があっても、そのために生命が脅かされることはありませんが、心房内の血液の流れが悪くなり、心房内に血栓ができやすくなり、それが脳に飛んで脳梗塞を起こすことがあります。左心房の一部に左心耳と呼ばれる部分があります。ここは丁度顔に耳が付いているように、心房の一部が耳のようになっているところで、もともと血液の流れが少ない部分なのですが、心房細動になると心房全体の収縮性が低下するため、左心耳内は血流がほとんどなくなり、血液がうっ滞して血栓(血のかたまり)ができてしまうのです。この血栓が何かの拍子に剥がれると、血液の流れに乗って左心房→左心室→大動脈→頸動脈→大脳動脈と進み、脳動脈の途中で詰まって脳梗塞を起こすのです。 心房細動の治療には、肺静脈にある心房細動の原因から心房を隔離するカテーテルアブレーションによる治療と、症状や発作を抑える薬物治療があります。症状が軽い場合には。脳卒中を予防するために抗血栓薬を服用します。 心房細動とよく似たものに心房粗動があります。心房細動に比べて心房の震え方がもう少し粗く、したがって脈拍も心房細動ほど不規則ではなくなります。心房粗動の治療も、薬物治療とカテーテルアブレーションによる治療があります。図は日本心臓財団ハートニュース60号より

アルコールと健康の関係は? 「酒は百薬の長」は本当か- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2014年07月25日アルコールと健康の関係は? 「酒は百薬の長」は本当かキーワード:二少(少食・少酒) 心筋梗塞/狭心症 脳梗塞/脳出血 脂肪肝/NAFLD/NASH アルコール性肝炎 三多(多動・多休・多接) アルコールが健康にもたらす影響が注目されている。米国では、アルコールが原因で死亡する人が年間約9万人に上るという調査結果が発表された。日本でも、アルコールがもたらす社会問題の解決に向け「アルコール健康障害対策基本法」が2014年6月1日に施行された。アルコールの害についてあらためて考えてみた。アルコールの7つの害 飲み過ぎに注意 アルコールは、「酒は百薬の長」といわれるように、適量を守れば、血行を促進し緊張感を和らげ、体に良い働きをもたらす。国立がん研究センターの調査では、適量の飲酒を続けている人では、脳卒中の発症が4割低下することが示された。この理由

楽天的な人の方が健康的に生きられる プラス思考は心臓に良い- 日本生活習慣病予防協会 -
や血糖値、コレステロール値、BMIなどが良好で、喫煙率が低い傾向があることが示された。これらの値が正常ということは、心臓病など循環器系疾患リスクが低いことを示す。 もっとも楽観度が高いグループは、もっとも悲観的なグループに比べ、総合健康スコアが「正常」である割合が2倍に上昇した。 運動は健康状態を改善するとともに、楽観的な気分を高める効果がある。運動を行うことで、メンタル面での向上もはかれ、相乗的な効果を期待できる。 うつ状態、怒り、不安、敵意、ストレスのようなネガティブな精神状態が、心臓と血管の健康に有害であることは、多くの研究で示されている。 デンマークで行われた虚血性心疾患のある患者600人を対象に行った調査でも、楽観的な患者はそうでない患者よりもよく運動しており、追跡期間中に死亡リスクが42%低下したことが明らかになった。 「血圧値やコレステロール値、血糖値が高く、BMIの高い肥満の人は、心臓病を発症する危険性が高い。今回の研究結果は、これらの数値の改善に加えてメンタル面でアプローチすることが健康増進に役立つことを示唆しています」と、イリノイ大学のロザルバ ヘルナンデス教授は言う。 研究者は保健指導を行うときに、運動習慣の指導に含めて、生活に対して楽観的であるかを聞くことの重要性も指摘している。心臓病を予防するための「ライフ シンプル セブン」 米国心臓学会が提唱する「ライフ シンプル セブン」では、心臓病や脳卒中を予防するのに効果的な7つの生活スタイルをアドバイスしている。下記の指標を14点満点で採点し、点数が1点増えると心臓病や脳卒中のリスクが8%減少するという調査結果がある。(1) 血圧をコントロールする 高血圧は自覚症状が乏しいので、自分が高血圧だと気づいていない人も多くいる。40歳以上の男性の6割以上が高血圧で、一生のうちに9割の人が血圧が高くなるという調査結果がある。家庭用血圧計を使い、朝と夜寝る前に血圧を測ってみよう。 健康な体重を維持すること、塩分の摂取量を減らすこと、医師に処方してもらった薬をきちんと飲むことが大切だ。(2) 標準体重を維持する 脂肪が一定以上に多くなり、心臓の負担が増えている状態が肥満。肥満に脂質異常や、高血圧、高血糖などが重なると、心臓の負担はさらに増える。体重を落としただけでも、これらの検査値は改善する。 1日の食事で必要なカロリーを確かめて、それを超えて食べ過ぎないようにし、有酸素運動を習慣として行えば、体重を減らすことができる。(3) 血糖値を下げる 糖尿病のある人では、心臓病や脳卒中の危険性が4倍以上に高まる。血糖値をコントロールすれば、これらの合併症を防ぐことができる。糖尿病は食事や運動の影響を受けやすい病気だ。生活習慣を少しずつでも改善していき、医師から処方された薬をしっかり飲むことで糖尿病を改善できる。(4) コレステロールを管理する コレステロールの異常は、死因の上位を占める