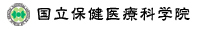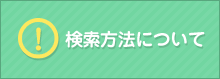病気の解説「前立腺癌」での検索結果

がんのリスクは糖尿病予備群の段階で上昇 軽く考えずに対策を- 日本生活習慣病予防協会 -
などの原因になる動脈硬化も進行しやすくなる。 今回の研究では、糖尿病予備群の人では、がんの発症も増えることが判明した。これらの病気を予防するためには、糖尿病予備群の段階で、食事を見直したり、体重増加や運動不足にならないように生活習慣を見直すことが必要となる。 健診などで糖尿病予備群と指摘されたら、軽く考えずに医師の指導を受けることが大切だ。糖尿病予備群ではがん発症リスクが15%上昇 研究は、中国順徳第一人民医院のユリ ヒュアン氏らによるもので、欧州糖尿病学会(EASD)が発行する医学誌「ダイアベトロジア」に発表された。 世界中で計89万1,426人を対象に行われた16件の研究結果を分析したところ、糖尿病前症の状態にある人ではそうでない人に比べ、全がん発症リスクが15%高いことが判明した。 がんの部位別にみると、相対リスクは胃がんと大腸がんで1.55倍、肝臓がんで2.01倍、膵臓がんで1.19倍、乳がんで1.19倍、内膜がんで1.60倍にそれぞれ上昇していた。気管支・肺がん、前立腺がん、卵巣がん、腎臓がん、膀胱がんではリスクの上昇はみられなかった。 肥満になるとがんを発症するリスクが上昇することから、体格指数(BMI)を調べた研究のみを解析したところ、肥満のある糖尿病予備群では全がん発症リスクは22%高いことが分かった。がんと糖尿病の原因は共通している なぜ血糖値が高いとがんの発症リスクが上昇するのか、研究者は3つのメカニズムで説明が可能と解説している。いずれも加齢に伴い影響が大きくなる要因だ。 ひとつは、糖尿病予備群の段階で、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きにくくなる「インスリン抵抗性」が亢進しており、血中のインスリン濃度が高くなり、がん細胞の成長が促されるからだという。 また、「AGE」はがん発症に関わる物質として注目されている。AGEとは「終末糖化産物」、すなわち「タンパク質と糖が結合してできた物質」のこと。強い毒性を持ち、老化を進める原因物質とされている。血糖値が高い状態が続くと、AGEが体にたまりやすくなり、がんの発症を引き起こしている可能性がある。 さらに、過剰なカロリー摂取によって、がん細胞の増殖を抑える「がん抑制遺伝子」の作用が弱くなることも原因となっている可能性がある。 「糖尿病の有病者と予備群の数は世界的に増えています。糖尿病とがんを引き起こす要因は共通するものが多くあります。多くは生活スタイルを健康的に変えることで改善が可能です。糖尿病予備群の段階で糖尿病に対策することが、公衆衛生上の大きな利益をもたらします」と、ヒュアン氏は強調する。 なお、過去の研究では、糖尿病の治療薬としてもっとも多く使われている「メトホルミン」が、がんの発症リスクを約30%低下させると報告されている。 「メトホルミンは広く利用されている薬剤であり、がんの抑制に役立てられると期待できます。ただし、糖尿病予備群の段階でこの効果が得られるかを、大規模な研究で確かめる必要があります」と指摘している。Prediabetes

がん10年生存率を初公開 がん生存率は年々向上 全部位は58.2%- 日本生活習慣病予防協会 -
%)」「甲状腺(91.6%)」。次いで、「子宮体(84.9%)」「大腸(75.9%)」「子宮頸(75.1%)「胃(73.1%)」が70%以上を保持している。「卵巣(61.0%)」「肺(43.9.%)」「食道(42.3%)」「肝(34.8%)」などが続く。一方、「胆のう胆道(28.9%)」「膵(9.1%)」は3割以下にとどまっている。全がん協部位別臨床病期別5年相対生存率(2004-2007年診断症例)出典:全がん協加盟施設の生存率協同調査(2015年)部位ごとの10年相対生存率 全部位は58.2% 今回がはじめて集計となる全部位全臨床病期の10年相対生存率は58.2%だった。同じデータベースの5年相対生存率は63.1%となっており、5年間で4.9%の減少がみられる。 10年生存率において高い生存率をみせた部位は、「甲状腺(90.9%)」「前立腺(84.4%)」「子宮体(83.1%)」「乳(80.4%)」「子宮頸(73.6%)」など。「大腸(69.8%)」「胃(69.0%)」「腎(62.8%)」「卵巣(51.7%)」などが続く。逆に「肺(33.2%)」「食道(29.7%)」「胆のう胆道(19.7%)」「肝(15.3%)」「膵(4.9%)」などは低い数値となった。 5年後、10年後の両方を見ての生存率では、乳がんはマンモグラフィー検診の普及などにより10年生存率でも80.4%と高い。前立腺がんも、腫瘍マーカーの普及で早期発見が可能になり、「病期1」でがんが見つかったケースでは生存率は10年近くまででほぼ100%に上る。一方、肝臓がんと膵臓がんの生存率は時間の経過とともに目立って低下する。全がん協部位別臨床病期別10年相対生存率(1999-2002年初回入院治療症例)出典:全がん協加盟施設の生存率協同調査(2015年)インターネットで公開 がん治療法選択の判断の目安に なお、研究班は今回の結果をKapWebに反映させて公開。「がんの種類」「病期」「治療法」などの条件設定で検索でき、5年もしくは10年までの生存率年次推移をグラフで見られる。 今回、10年相対生存率のほか、新規診断症例、治療法の選択項目が追加され、より詳細な条件設定が可能となった。「どの治療法を選んだら生存率が高くなるかを知る

新規がん患者は88万人に増加 国立がん研究センターが初の予測- 日本生活習慣病予防協会 -
,500人)は近い将来、胃がんを上回ると予想される。男女別では、男性で胃がん、肺がん、前立腺がんの順、女性で乳がん、大腸がん、胃がんの順で多かった。 死亡数では肺がんがもっとも多く7万6,500人で、2位の胃がん(5万300人)、3位の大腸がん(4万9,500人)を大きく引き離した。治療の難しい膵臓がんの死者数は3万1,900人で、今回5位となった肝臓がん(2万9,700人)と入れ替わって4位になった。 予測は、1975年以降のがんの推移をもとに、人口の高齢化なども考慮して予測した。がんに関する毎年の統計データは、全国がん罹患モニタリング集計にもとづく患者数が4〜5年遅れ、人口動態統計による死亡者数が1〜2年遅れで発表されている。 がん患者は転移や再発、多重がんなどで複数の医療機関を受診することが多く、死亡情報との整理・照合に時間がかかるためで、データの把握と対策との時間差が懸念されていた。 同情報センターは今後、毎年春にその年の予測数を公開する。「予測精度を検証しつつ、ニーズにそったがん統計情報を整備していく。国や地域のがん対策の目標設定や評価に活用してもらいたい」としている。国立がん研究センターがん対策情報センター がん情報サービス(Terahata)◀ 前の記事へ次の記事へ ▶ 関連トピック

人間ドック:昨年の受診者で「異常なし」は過去最低の8.4%- 日本生活習慣病予防協会 -
代が5.6%、60歳以上が3.7%だった。 低い年齢層では、生活習慣の改善を求められる程度の軽い異常値の人が比較的多かったが、高齢者になるほど治療が必要な人の割合は増える傾向がみられる。男女別では、男性7.3%、女性10.2%だった。 生活習慣病と関連の深い検査6項目で比較すると、異常があった検査項目は多い順に、肥満(27.7%)、高コレステロール(27.3%)、肝機能異常(27%)、耐糖能異常(20.3%)、高血圧(18.8%)。 生活スタイルと関連の深いこれらの検査項目で、前年より減少したのは高中性脂訪のみで、5項目ではすべてが増加した。 性別にみると、男性では肥満が32.9%ともっとも多く、以下は肝機能異常、高コレステロール、耐糖能異常、高血圧と続く。 女性では高コレステロールがもっとも多く26.7%を占め、肥満、肝機能異常、耐糖能異常、高血圧と続く。女性では高コレステロールの異常の割合が、50歳代以後に急上昇して男性と逆転した。 男性では年齢層別にみると、耐糖能異常と高血圧は加齢とともに上昇傾向を示し、肝機能異常、肥満、高コレステロール、高中性脂訪は50歳代をピークとして、60歳以上は下降傾向を示している。 地域別では、健常者の割合が最低の地域は九州・沖縄地方の5.7%、最高は中国・四国地方の13.3%だった。その他は北海道が7.6%、東北が9%、関東・甲信越が8.1%、東海・北陸が8.3%、近畿が7.8%となっている。 地域差を年別に比べると、東海・北陸、近畿、九州・沖縄地方は前年よりやや増加し、その他の地域は前年より低下。特に関東・甲信越と北海道地方の低下は顕著だった。がん:人間ドックは「総合型検診」、軽症のうちに発見・治療 発見がん症例数も前年より増加した、人間ドックで発見されるがんのトップは胃がん(28.2%)であり、次いで大腸がん(16.5%)。両方を合せると25年前は全発見がんの約70%を占めていたが、今回の調査では約45%と年々減少傾向を示している。 その理由は、その他のがんが年々増加し、特に男性では前立腺がん、女性では乳がんが著しく増えたため。女性に限ると乳がんは41.7%でトップ。 同学会では「日本人の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人はがんで死亡しているのが現状」として、がんを発見した症例数の増加について「人間ドック健診施設の質的向上がうかがわれる」と指摘している。 住民を対象としたがん検診は、特定臓器に限定しているに対し、人間ドックは「個別型がん検診」で、オプション検査を含めて全臓器を対象とした「総合型検診」と説明している。 人間ドックで最も発見頻度の高い胃と大腸がんについては、早期がんの占める割合が72〜77%前後。胃は94%、大腸がんの97%が手術を実施しており、特に大腸がん手術例中内視鏡的切除が年々増加して7害リを占め、「二次予防の有用性を実証することができた」と述べている。 死因のトップを占めているがん死亡率を今後

生活スタイルの改善が遺伝子を変える 5年間でテロメアが10%延長- 日本生活習慣病予防協会 -
や生活での不安、悩み、ストレスについて相談できる人をもつことは重要。グチやボヤキでもよいので、相談相手をつことが、ストレス管理の改善につながる。 ソーシャルメディアを活用して話し合える相手をもつこともひとつの方法だ。 オーニッシュ氏ら研究チームは、危険性の低い前立腺がんと診断された男性35人を対象に実験を行った。被験者を2群に分け、10人には生活を全体的に見直し、生活スタイルの改善に努めてもらった。25人は従来通りの生活をした。 生活スタイルを改善した群は、週に1回のミーティングに参加してもらい、専門家より生活改善の指導を受けてもらった。参加者は多くの場合、意欲的に参加したという。 5年後に被験者の血液サンプルを採取し、テロメアの長さを測定したところ。生活スタイルを改善した群では、テロメア長さが平均10%増加していた。対照群では平均3%縮小していた。 「生活スタイルを健康的に変えていくことは、もっとも効果的な薬になります。わずか5年間という短い期間でも、健康的な生活を選んだ人では、テロメアはより長くなりました」と、オーニッシュ氏は強調する。 今回の研究は予備的に行われたものだが、今後の大規模な無作為化比較試験への期待を抱かせるのに十分なものだったという。 「老化を促す要因を取り除くことで、体に備わっている治癒力は強められます。このメカニズムはとてもダイナミックで、短い期間で体を変えることが可能であることが、研究で示されました。大変に感慨深いことです」と、オーニッシュ氏は述べている。Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study(Lancet Oncology 2013年9月17日)予防医学研究所(PMRI)(Terahata)◀ 前の記事へ次の記事

ハムやソーセージを食べるとがんリスク上昇 肉類は「発がん性あり」- 日本生活習慣病予防協会 -
を50g増えると、結腸がんになる相対リスクは18%上昇するという。 研究グループによると、加工肉の多くは塩分や脂肪を加えてあり、保存剤を加えてあるものがある。また、動物性脂肪を消化する過程でできる胆汁酸やヘム鉄に酸化作用があり、肉の焦げた部分に発がん物質が含まれる 加工していない赤身肉(牛肉、豚肉、羊肉など)については「グループ2A」に分類され、「発がん性がおそらくある」と評価された。 1日に食べる赤身肉の量が100g増えると、結腸がんを発症する相対リスクは17%上昇するという。結腸がんのほかに、膵臓がんや前立腺がんとも関連があることが示された。日本人でも肉類の食べ過ぎるとがんリスクが上昇することが判明 「2013年国民健康・栄養調査」によると、日本人が1日に食べる肉類全体の摂取量は平均89.6gで、そのうちハム・ソーセージ類の摂取量は平均12.9gだ。 日本人の平均的な肉類の摂取量は欧米に比べ少ないので、ほとんどの人は食べ過ぎに注意していれば、がんの発症リスクは上昇しないことになる。 日本では、国立がん研究センターが中心となり、大規模コホート研究「JPHC研究」が行われ、加工肉や赤身肉の摂取とがんの発症リスクについて調査した。 研究チームは、約8万人の日本人を2006年まで約10年間追跡して調査した。その結果、肉類を1日100g以上食べている男性は結腸がんの発症リスクが1.44倍に上昇し、赤身肉を1日80g以上食べている女性は結腸がんの発症リスクが1.48倍に上昇することが示された。 ハムやソーセージなどの加工肉については、日本人の平均的な摂取量であれば、結腸がんや直腸がんの発症リスクの上昇につながらないことも分かった。 JPHC研究では、牛や豚の赤見肉をたくさん食べる男性は、ほとんど食べない男性に比べ、糖尿病を発症するリスクが4割高まることも示されている。 「飲酒、肥満は大腸がんリスクを増大させ、運動はリスクを低下させることが確実と評価されています。これらの生活習慣に気を配ることが、肉の過剰摂取を避けることと合わせて、がんの予防には大切です」と、研究チームは指摘している。肉は体に必要な栄養の供給源と主張 IARCは、世界のがん死亡患者のうち年間約3万4,000人が加工肉の多い食生活が原因でがんを発症したとする研究結果を紹介している。 一方、年間のがん死亡患者のうち、喫煙が原因とみられるのは100万人、アルコール摂取は60万人、大気汚染は20万人で、これらに比べると肉の摂取が原因のがんは少ない。 IARCの発表を受け、北米食肉協会(NAMI)は「肉は栄養価が高く、良質なタンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンB群などの栄養素の供給源になります。また、肉を過剰摂取

生活を改善すれば細胞の老化を防げる 高カロリーの食品が害に- 日本生活習慣病予防協会 -
れるというカリフォルニア大学の研究が発表された。炭酸飲料を飲み過ぎると、喫煙に匹敵するダメージが細胞にもたらされるという。 細胞には寿命があり、これには染色体の「テロメア」と呼ばれる塩基配列が関わっている。テロメアは染色体に備わった"靴ひもの先端"のようなもので、限度以下に短くなってしまうと、細胞はそれ以上分裂できない。 テロメアの長さは寿命に関係する。その長さはさまざまな生活スタイルによって変化し、同じ年齢であってもテロメアの短い人は、加齢にともなう心臓病、2型糖尿病、がんなどの慢性疾患を発症しやすくなると考えられている。 カリフォルニア大学の研究チームは、糖尿病や心臓病の病歴をもたない5,309人の20〜65歳の米国人を対象にした米国健康・栄養調査(NHANES)の1999年から2002年のデータを分析した。その結果、糖分を多く含む炭酸飲料を多く飲む人ほど、テロメアが短くなる傾向があることが判明した。 調査によると、1日に227mL(8オンス)の炭酸飲料を飲んでいる人では、白血球の染色体のテロメアは短くなり、実際の年齢よりも1.9歳分も老化していることが分かった。炭酸飲料を飲む量が増えるとより短くなり、567mL(20オンス)を飲むと4.6歳分、老化が余分に進む計算になるという。 「糖分の多い高カロリーの炭酸飲料を飲み過ぎると、体内のブドウ糖の代謝をコントロールする働きが悪くなるだけではなく、細胞の老化が促進されることが明らかになりました」と、研究を主導したエリッサ エペル教授は話す。 「テロメアの短縮は細胞の老化だけでなく、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きが悪くなる"インスリン抵抗性"や、内臓脂肪細胞などから分泌され、体内のさまざまな炎症を引き起こす"炎症性サイトカイン"にも影響します」。生活スタイルを改善すればテロメアを長くできる テロメアが長いほど病気になりにくく、寿命も長いことが示されている。カリフォルニア大学の研究では、健康的な食事と運動、ストレスの管理によって、テロメアを伸ばせることが示された。 「"遺伝子によって寿命は決められてしまうので、どうすることもできない"と考える人が少なくありませんが、生まれもっている遺伝子とテロメアは必ずしも運命を決定しません。生活スタイルの改善によって、テロメアが長くなる可能性が示されています」と、カリフォルニア大学予防医学研究所のディーン オーニッシュ教授は言う。 研究チームは、さまざまな生活スタイルがテロメアに及ぼす影響や、テロメアを長くする酵素の活性などを調査した。研究には35人の初期の前立腺がん患者が参加し、うち10人は5年間にわたって生活スタイルを改善する介入を受けた。 その結果、生活スタイルを改善した介入群では、改善しなかった対照群に比べ、なんとテロメアの長さが平均約10%も伸びていたという。生活スタイルをより積極的に改善した人ほど、テロメアが劇的に長くなっていた。一方、何もしなかった対照群ではテロメアが3%ほど短くなっていた。 テロメアを長くするのに効果的な生活スタイルは次の通り

ウォーキングが13種類のがんのリスクを減少 30分の運動でがんを予防- 日本生活習慣病予防協会 -
一方で、運動する頻度の高い人では、「悪性黒色腫」(メラノーマ)や前立腺がんの発症リスクが高いことも明らかになった。 メラノーマについては、「運動をよくする人は外に出る機会が多い傾向にあり、日焼けによって皮膚がんを発症するリスクが上昇するおそれがある」と、ムーア氏は説明する。 ただし、よく運動する人は健康診断を受ける回数が多い傾向があり、がんの発見率が高いことが影響している可能性もあるという。そうした場合、自覚症状がない軽症のうちにがんが発見でき、早期に治療を開始できる。 実際に欧米では、がん検診の受診率が向上した結果、がんの発症率は増えているが死亡率は減少している傾向がみられるという。 世界保健機関(WHO)は、世界のがんの新規疾患数は年間に1,406万件(2012年)で、今後20年間で2,200万件に増加すると予測している。 「適度な運動をすることががんを予防するために効果的です。それに加えて、適正体重を維持する、たばこを吸わない、アルコールを控える、健康的な食生活に変えるといった生活スタイルを加えるべきです」と、ムーア氏は指摘している。 Increased physical activity associated with lower risk of 13 types of cancer(米国立衛生研究所 2016年5月16日) Association of Leisure-Time Physical Activity With Risk of 26 Types of Cancer in 1.44 Million Adults(JAMA Internal Medicine 2016年5月16日) (Terahata) ◀ 前の記事

職場のがん検診 女性の受診率は3割台どまり 精密検査も伸び悩み- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2016年05月18日 職場のがん検診 女性の受診率は3割台どまり 精密検査も伸び悩み キーワード:がん 健診・保健指導 女性の健康 厚生労働省は、企業の健康保険組合が実施するがん検診の実態調査の結果を公表した。胃がん、肺がん、大腸がんなどの検診の受診率は高いものの、女性の乳がんや子宮頸がんなどの検診受診率は伸び悩んでいる。「異常あり」と判定された場合の精密検査の受診率の向上も課題となっている。 職場のがん検診 精密検査の受診率が伸び悩んでいる 厚生労働省は、企業の健康保険組合が実施するがん検診の実態調査の結果を公表した。健康診断などの機会にがん検診を受診している従業員の割合は、胃がん、肺がん、大腸がんでは6?7割と高い一方、乳がんや子宮頸がんなどの女性の検診受診率は3割台にとどまっていた。同省が職場のがん検診に関する実態調査をしたのは今回がはじめて。 調査は昨年12月~今年1月、全国の1,406の健康保険組合にアンケートを送付、1,238の組合から回答を得た。▽胃がん、▽肺がん、▽大腸がん、▽乳がん、▽子宮頸がん、▽前立腺がん、▽肝臓がん、▽甲状腺がん

がん発症数が増加 はじめて80万人超 がんを予防するための5ヵ条- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2014年06月19日がん発症数が増加 はじめて80万人超 がんを予防するための5ヵ条キーワード:二少(少食・少酒) がん 「無煙」喫煙は万病の元 三多(多動・多休・多接) 1年間に新たにがんを発症した人は、2010年の推計値で80万人を超えたことが、国立がん研究センターがん対策情報センターの最新の統計調査で明らかになった。日本人のがん発症が80万人を超えたのははじめて。生涯でがんを発症する確率は男性60%、女性45%としている。がんの発症数は25年で2.4倍に増加 高齢化が影響 がんの発症数と死亡数は、高齢者の増加を主な要因として、ともに増加し続けている。一方でがんの治療は進歩しており、生存率(あるがんと診断された場合に、治療でどのくらい生命を救えるかを示す指標)は伸びている。 2010年にがんを発症した人は、男性が46万8,048人、女性が33万7,188人の計80万5,236人。1985年の33万1,485人の約2.4倍に増えた。 発症した人が多いがんを部位別にみると、男性は(1)胃がん(18.5%)、(2)肺がん(15.8%)、(3)大腸がん(14.5%)、(4)前立腺がん(13.9%)、(5)肝がん(6.7%)となっている。 女性は(1)乳がん(20.2%)、(2)大腸がん(15.1%)、(3)胃がん(11.6%)、(4)肺がん