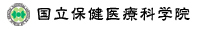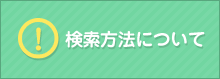病気の解説「前立腺癌」での検索結果

リノール酸を含む植物油は体に良い 脂肪の摂取バランスが大切- 日本生活習慣病予防協会 -
ます」(フリッチェ氏)。 一方で、リノール酸などの植物油をとりすぎると、乳がん、前立腺がん、大陽がんなどの発症率や死亡率が上昇するという研究が過去に発表されたことがある。 「今回に研究では、リノール酸の摂取とがん発症と関連があるという結果は示されませんでした」と、フリッチェ氏は述べている。オメガ6系脂肪酸はLDLコレステロールを低下させる 脂肪の中には、体内で作ることができず食物からとらなければならない必須脂肪酸があり、その代表が「オメガ3系脂肪酸」と「オメガ6系指肪酸」だ。 不飽和脂肪酸には、二重結合が1ヵ所の「一価不飽和脂肪酸」と、2ヵ所以上ある「多価不飽和脂肪酸」がある。不飽和脂肪酸の単位記号として用いられるのが「オメガ」で、最初の二重結合が末端の炭素(オメガ炭素)から数えて6番目にあるものが「オメガ6系脂肪酸」と呼ばれる。 植物油に含まれるオメガ6系脂肪酸には、菜種油、大豆油などに含まれるリノレン酸や、コーン油、紅花油、ヒマワリ油、トウモロコシ油、ゴマ油、マーガリンなど植物油全般に含まれるリノール酸がある。 家庭で炒め物や揚げ物などの調理に使われる植物油はリノール酸が多い。日本ではリノール酸の消費が多く、日本人が摂取しているオメガ6系脂肪酸の9割以上はリノール酸だ。 リノール酸は体内で合成できず、食事から摂取する必要があるため、必須脂肪酸と呼ばれる。適量のリノール酸を摂取すると「総コレステロール値やLDLコレステロール値が低下し、心臓病の予防につながる」とされている。脂肪の摂取バランスを考え、食生活を見直すことが重要 健康増進の効果があると注目されているもうひとつの脂肪が、オリーブ油や魚油、ナッツ類などに含まれる「オメガ3系脂肪酸」だ。 「オメガ3系脂肪酸」には、リノレン酸、エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA)などの種類がある。血液の流れを妨げるLDLコレステロールや中性脂肪を減らす働きをし、動脈硬化や心筋梗塞、脳血栓などを防ぐとされている。 「オメガ3系脂肪酸が有用なことはよく知られていますが、バージンオイルなど、限られた食品にしか含まれていないという欠点があります。これらの食品の多くは高価で、利用できる人が限られています」と、フリッチェ氏は指摘する。 オメガ3系脂肪酸に比べると、リノール酸の含まれる植物油は安く利用でき、どこでも入手できるというメリットがある。「食事から摂取する飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸のバランスが、LDLコレステロール値に影響します。動物油を植物油に置き換えるだけでも、値康増進の効果を期待できます」と、フリッチェ氏は強調する。 「脂肪酸の機能性に関心をもち、植物油とともに野菜の摂取量を増やすなど、食生活全体を見直すことが重要です」とまとめ

人間ドックで全項目異常なしの「スーパーノーマル」が過去最低の6.6%- 日本生活習慣病予防協会 -
は、受診者の高齢化、検査項目の増加、判定基準の厳格化などが影響していると指摘している。 人間ドックの普及に伴い、反復受診者の割合は全受診者の70~80%を占めるようになり、その結果、人間ドック受診者の平均年齢が40歳代から50歳代へと移行し、さらに60歳以上の受診者が年々増加しているという。 生活習慣病関連項目の異常頻度を経年でみると、肝機能異常、高コレステロール、肥満、耐糖能異常、高血圧が年を経るごとに増加しており、特に耐糖能異常と高血圧は2005年以降、急速に増えている。がん検診は人間ドックではオーダーメードに対応 人間ドック健診で発見されるがんのトップは胃がんであり、次いで大腸がんで、近年は特に男性では前立腺がん、女性では乳がんの増加傾向がみられる。 その理由として、男性についてはPSA検査が1995年に導入されたことと、女性については乳房のエコー検査やマンモグラフィ—といった画像検査が普及してきたことが挙げられる。 住民を対象とした「対策型がん検診」は特定臓器に限定しているのにに対し、人間ドックは「個別型がん検診」で、オプション検査を含めて全臓器を対象とした「総合型検診」であるという特徴がある。 同学会は、「50歳以上の男性に対してPSA検査、40歳以上の女性には乳房エコー検査やマンモグラフィーを基本検査項目に導入する必要がある」と指摘。また、ハイリスクグループの選別による有効的ながん検診を行うことにより、さらなる発見率の向上を期待できるとしている。 具体的には、喫煙者に対する胸部CT検査や人間ドック受診者数の多い施設では、ピロリ菌抗体(HP)検査と血清ペプシノゲン(PG)法により胃内視鏡検査を選択することが有効な方法となるという。人間ドック学会(Terahata)◀ 前の記事

薬物療法(化学療法)- 国立がん研究センター -
に対して、動注療法が適用されます。また、上顎(じょうがく)がんなどの頭頸部(とうけいぶ)がん、骨腫瘍、卵巣がん、膀胱(ぼうこう)がん、前立腺がん、膵(すい)がん、さらには進行した乳がん等にもこの動注療法が用いられることがあります。 経口投与は患者さんにとって便利な投与方法ですが、消化管からの吸収量に個人差が大きいため、開発が難しいとされています。また、飲み忘れといったことも起きやすいため、患者さんの十分な理解が必要になります。 7.がん治療における薬物療法の目的 がん治療の最大の目的は、患者さんの生命を保つことです。場合によっては、がんの増殖を遅らせること、がんによる症状から解放すること、全身状態(QOL:クォリティ・オブ・ライフ:生活の質)の改善等を目的とすることがあります。治療内容は、最善のものが選ばれるようになっています。どんな治療が最善かは、その方の生活信条や生活習慣により異なります。がんの治療は、日々進歩しています。治療方針を決定するため、治療法についての正確な知識が主治医より説明されます。いろいろな治療法が登場していますが、どの治療法にも適応(有効)と限界があり、すべてに有効という完全な治療法はまだありません。1つの治療法では完治が望めない場合には、いくつかの治療法を組み合わせ、それぞれの限界を補いあって治療しようという研究が行われています。このような治療法を、「がんの集学的治療」と呼んでいます。 8.化学療法で治癒可能ながん 抗がん剤で完治する可能性のある疾患は、急性白血病、悪性リンパ腫、精巣(睾丸)腫瘍、絨毛(じゅうもう)がん等です。わが国におけるこれらのがんによる死亡者数は、1年間に15,000〜16,000人です。胃がんや肺がんの年間死亡者数は、それぞれ70,000人と50,000人ですから、それらに比べると比較的まれな疾患ということができます。また、病気の進行を遅らせることができるがんとしては、乳がん、卵巣がん、骨髄腫(こつずいしゅ)、小細胞肺がん、慢性骨髄性白血病、低悪性度リンパ腫等があります。投与したうちの何%かで効果があり症状が和らぐというのが、前立腺がん、甲状腺がん、骨肉腫、頭頸部がん、子宮がん、肺がん、大腸がん、胃がん、胆道がん等です。効果がほとんど期待できず、がんが小さくなりもしないというがんに、脳腫瘍、黒色腫、腎がん、膵がん、肝がん等があります。 ところで、治療を受ける前に抗がん剤が効くか効かないかを予想できれば理想的です。例えば感染症に対する抗生物質では、あらかじめその抗生剤が感染症の原因となっている病原菌に効くかどうかを検査したうえで、投与する場合があります。そのようなことが抗がん剤でできないのかという疑問が、当然出てきます。投与する前に行う「抗がん剤感受性テスト(がん細胞と抗がん剤を接触させ、増殖の抑制をみる検査)」というものがありますが、現在のところこの検査の有効性は不十分で、一般的には用いられていません。 化学療法で治癒が可能ながんと、化学療法の効果の特徴をあげてみましょう。 1)小児の急性リンパ性白血病 5年

「男のストレス」ががんリスクを高める 肝臓がんは33%上昇- 日本生活習慣病予防協会 -
したもの。産業医の8割が「メンタルヘルス不調・過労対応に自信がない」うつ病の予防に週1時間の運動 ウォーキングは気分を明るくする「肥満」と「うつ病」のダブルパンチ 体重コントロールは脳にも良い自覚的ストレスレベルが高い男性はがんリスクが19%上昇 研究チームはまず、調査の開始時に「日常あなたの受けるストレスは多いと思うか?」というアンケートを実施。その回答をもとに、日常的に自覚するストレスの程度について3つのグループに分けた。 日常的に自覚するストレスが「低」の人は1万6,167人、「中」の人は6万4,180人、「高」の人は2万1,361人だった。 アンケートは、調査開始5年後も実施した。両方のアンケート回答者(7万9,301人)の自覚的ストレスに関する回答の組み合わせから、その変化を6つのグループ(常に低、常に低・中、常に中、高が低・中に変化、低・中が高に変化、常に高)に分けた。 期間中に1万7,161人ががんを発症。がん罹患リスクとの関連を検討した結果、「常に自覚的ストレスレベルが高いグループ」は、「常に自覚的ストレスレベルが低いグループ」に比べ、全がん罹患リスクが11%高いことが分かった。 特にその傾向は男性で強くみられ、自覚的ストレスが高いと、男性で19%、女性で7%、全がんリスクがそれぞれ上昇した。 罹患したがんを臓器別にみると、肝臓がんで33%、前立腺がんで28%、膵臓がんで26%、それぞれリスクが高くなることが判明した。男性はストレスによる生理的影響を受けやすい 研究チームは、がんのリスクを高める喫煙や飲酒など生活習慣の影響を除いて分析しており、同じ多量飲酒者や喫煙者の中でもストレスが多い人の方ががんのリスクが高かった。 「男性は女性よりもストレスによる生理的影響を受けやすい可能性があります。また、ストレスレベルが高い男性は、喫煙や飲酒など、がんのリスク要因となる生活習慣をもつ傾向が強い」と、研究チームは述べている。 ストレスががんを引き起こすメカニズムは詳しくは分かっていないが、動物実験では、免疫機能の低下を通じて他の肝疾患を発症し、発がんに至るという報告がある。肝がんは特にストレスの影響を受けやすい可能性があるという。多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究

日本の喫煙対策は遅れている 屋内では100%禁煙に たばこ白書を改定- 日本生活習慣病予防協会 -
では約60万人と報告されている。日本人の喫煙による年間死亡者は約13万人、受動喫煙では約1万5,000人と推計されている。 がんを部位別にみると、肺がん、口腔・咽頭がん、喉頭がん、鼻腔・副鼻腔がん、食道がん、胃がん、肝がん、膵がん、膀胱がん、子宮頸部がんについては、喫煙との因果関係が「レベル1(十分)」と判定した。 喫煙と大腸がん、乳がん、子宮体がん、腎盂尿管・腎細胞がん、前立腺がん死亡、急性骨髄性白血病については「レベル2(示唆的)」と判定。 また、喫煙は循環器疾患も引き起こす。3つの疾患(虚血性心疾患、脳卒中、アテローム性動脈硬化症)について評価したところ、虚血性心疾患、脳卒中、腹部大動脈瘤、末梢性動脈硬化症について、「レベル1(十分)」と判定した。 喫煙は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、呼吸機能低下、結核死亡も引き起こす。それぞれ「レベル1(十分)」と判定。 たばこは、2型糖尿病の発症とも関連がある。禁煙による糖尿病のリスクの減少について日本人を対象とした研究は多くないが、禁煙によって耐糖能異常が改善するなど、リスクが減少するのは明らかで、「レベル1(十分)」と判定された。 たばこは喫煙者以外にも受動喫煙の弊害をもたらす。受動喫煙によって肺がん(レベル1)、乳がん、鼻腔・副鼻腔がん(レベル2)のリスクがそれぞれ高まる。受動喫煙は虚血性心疾患と脳卒中のリスクも上昇させる(レベル1)。喫煙室を設置せず、屋内の100%禁煙化を目指すべき 2013年の国民健康・栄養調査によると、成人の喫煙率は約19%と近年減少傾向にあるが、若年者や女性では喫煙率が高い。 また、飲食店や職場などで受動喫煙する機会が多い。たばこを吸わない人の33%が職場で、47%が飲食店で、月1回以上受動喫煙すると回答した。家庭内でほぼ毎日受動喫煙している20歳以上の割合は9%に上る。 世界保健機関(WHO)は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(FCTC)を2005年に制定、2008年にはたばこ対策を7項目にまとめた「MPOWER」を作成した。 それによると、日本で達成度が高いのは「たばこの使用と予防政策のモニター」のみで、「受動喫煙の防止」「脱たばこ・メディアキャンペーン」「たばこの広告・販売・後援の禁止」の3項目は「最低」だ。 日本では、2013年の健康増進法や2015年の労働安全衛生法の改正により受動喫煙を防止することが「努力義務」とされた。学校や病院、官公庁などの禁煙化が進んできたが、喫煙室を設置してもたばこ煙の漏れが防止できないことや、喫煙可能な店舗での受動喫煙などの問題はいまだ残っている。 世界の49ヵ国では、医療機関や大学・学校、飲食店、公共交通機関などの公共の場で「屋内全面禁煙」とする法規制をしている。そうした国では、喫煙関連の疾患による入院リスクが減少したことが報告されている。 報告書では受動喫煙対策として「日本でも喫煙室を設置することなく、屋内の100%禁煙化を目指すべきだ」と強調している。喫煙対策は自治体の取り組みが先行 喫煙対策では地方自治体の取り組みが先行している。神奈川県は、2010年に「受動喫煙防止条例」を全国に先駆けて施行した。官公庁、病院、学校、物品販売店などを原則として「禁煙

「気管,気管支及び肺」の‘がん’による死亡数は年間7万3,396人、がんの中で最多 厚生労働省「平成26年 人口動態統計(確定数)の概況」より- 日本生活習慣病予防協会 -
人 肝及び肝内胆管の悪性新生物 ▶ 2万9,543人 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 ▶ 1万8,117人 膵の悪性新生物 ▶ 3万1,716人 喉頭の悪性新生物 ▶ 978人 気管,気管支及び肺の悪性新生物 ▶ 7万3,396人 皮膚の悪性新生物 ▶ 1,657人 乳房の悪性新生物 ▶ 1万3,323人 子宮の悪性新生物 ▶ 6,429人 卵巣の悪性新生物 ▶ 4,840人 前立腺の悪性新生物 ▶ 1万1,507人 膀胱の悪性新生物 ▶ 7,760人 中枢神経系の悪性新生物 ▶ 2,326人 悪性リンパ腫 ▶ 1万1,480人 白血病 ▶ 8,196人 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 ▶ 4,237人 その他の悪性新生物 ▶ 2万7,219人 ちなみに、‘がん’全体で死亡した人数を性別に見ると、男性は21万8,397人で全死因の33.1パーセント、女性は14万9,706人で24.4パーセントで、男女ともに死因別の第1位となっています。 ●情報ソース:平成26年(2014)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省) 関連する調査・統計 疾患で見る ▶ 肺がん 2017年01月26日 喫煙者の割合は男性30.1%、女性7.9% 平成27年 国民健康・栄養調査 2016年10月13日 気管、気管支及び肺の悪性新生物の年間医療費は4,315億円 平成26年度 国民医療費の概況

「気管,気管支及び肺」の‘がん’による死亡数は年間7万4,378人、がんの中で最多 厚生労働省「平成27年 人口動態統計(確定数)の概況」より- 日本生活習慣病予防協会 -
気管,気管支及び肺の悪性新生物 7万4,378人皮膚の悪性新生物 1,505人乳房の悪性新生物 1万3,705人子宮の悪性新生物 6,429人卵巣の悪性新生物 4,676人前立腺の悪性新生物 1万1,326人膀胱の悪性新生物 8,130人中枢神経系の悪性新生物 2,445人悪性リンパ腫 1万1,829人白血病 8,631人その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 4,174人その他の悪性新生物 2万7,743人 ちなみに、‘がん’全体で死亡した人数を性別に見ると、男性は21万9,508人で全死因の32.9パーセント、女性は15万838人で24.2パーセントで、男女ともに死因別の第1位となっています。 平成27年(2015)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省) ▶ 関連する調査・統計 疾患で見る ▶ 肺がん 2017年01月26日 喫煙者の割合は男性30.1%、女性7.9% 平成27年 国民健康・栄養調査 2016年10月13日 気管、気管支及び肺の悪性新生物の年間医療費は4,315億円 平成26年度 国民医療費の概況 2016年10月13日 「気管,気管支及び肺」の‘がん’による死亡数は年間7万4,378人、がんの中で最多 厚生労働省「平成27年 人口動態統計(確定数)の概況」より 2016年04月19日

大腸がんの年間死亡数、「結腸の悪性新生物」3万3,297人、「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」1万5,188人 厚生労働省「平成26年 人口動態統計(確定数)の概況」より- 日本生活習慣病予防協会 -
及び直腸の悪性新生物 ▶ 1万5,188人 肝及び肝内胆管の悪性新生物 ▶ 2万9,543人 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 ▶ 1万8,117人 膵の悪性新生物 ▶ 3万1,716人 喉頭の悪性新生物 ▶ 978人 気管,気管支及び肺の悪性新生物 ▶ 7万3,396人 皮膚の悪性新生物 ▶ 1,657人 乳房の悪性新生物 ▶ 1万3,323人 子宮の悪性新生物 ▶ 6,429人 卵巣の悪性新生物 ▶ 4,840人 前立腺の悪性新生物 ▶ 1万1,507人 膀胱の悪性新生物 ▶ 7,760人 中枢神経系の悪性新生物 ▶ 2,326人 悪性リンパ腫 ▶ 1万1,480人 白血病 ▶ 8,196人 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 ▶ 4,237人 その他の悪性新生物 ▶ 2万7,219人 ちなみに、‘がん’全体で死亡した人数を性別に見ると、男性は21万8,397人で全死因の33.1パーセント、女性は14万9,706人で24.4パーセントで、男女ともに死因別の第1位となっています。 ●情報ソース:平成26年(2014)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省) 関連する調査・統計 疾患で見る ▶ 大腸がん 2016年10月13日 結腸及び直腸の悪性新生物の年間医療費は5,701億円 平成26年度 国民医療費の概況 2016年10月13日 大腸がんの年間死亡数、「結腸の悪性新生物」3万4,338人、「直腸S状結腸移行部

大腸がんの年間死亡数、「結腸の悪性新生物」3万4,338人、「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」1万5,361人 厚生労働省「平成27年 人口動態統計(確定数)の概況」より- 日本生活習慣病予防協会 -
及びその他の胆道の悪性新生物 1万8,152人膵の悪性新生物 3万1,866人喉頭の悪性新生物 971人気管,気管支及び肺の悪性新生物 7万4,378人皮膚の悪性新生物 1,505人乳房の悪性新生物 1万3,705人子宮の悪性新生物 6,429人卵巣の悪性新生物 4,676人前立腺の悪性新生物 1万1,326人膀胱の悪性新生物 8,130人中枢神経系の悪性新生物 2,445人悪性リンパ腫 1万1,829人白血病 8,631人その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 4,174人その他の悪性新生物 2万7,743人 ちなみに、‘がん’全体で死亡した人数を性別に見ると、男性は21万9,508人で全死因の32.9パーセント、女性は15万838人で24.2パーセントで、男女ともに死因別の第1位となっています。 平成27年(2015)人口動態統計(確定数)の概況(厚生労働省) ▶ 関連する調査・統計 疾患で見る ▶ 大腸がん 2016年10月13日 結腸及び直腸の悪性新生物の年間医療費は5,701億円 平成26年度 国民医療費の概況 2016年10月13日 大腸がんの年間死亡数、「結腸の悪性新生物」3万4,338人、「直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物」1万5,361人 厚生労働省「平成27年 人口動態統計(確定数)の概況」より 2016年04月19日 大腸がんをはじめとする腸に関係するがんの総患者数は26万1,000人 厚生労働省「平成26年患者調査の概況

人間ドックで「異常あり」が9割 昨年の人間ドック受診者- 日本生活習慣病予防協会 -
だ。「異常なし」は25年で20%以上も減少 調査は全国の人間ドック受診者を対象に検査成績などを調べたもので、今回が26回目。対象となった人間ドック受診者数は前年より約6万人多い301万人だった。 働き盛りの人の健康度は年々悪くなり、各検査項目ごとの判定で「異常なし」と判定された人の占める割合は1984年の29.8%から、2009年は9.5%と20.3%減少した。 人間ドックの受診者の年代別傾向は50歳代>40歳代>60歳代以上>30歳以下の順で、前年と同じ傾向がみられた。最多は高コレステロール26.5% 生活習慣病に関連の深い検査6項目をみると、男性では40〜50歳代で異常が増え、高血圧と高血糖は60歳以上でさらに増える傾向がある。女性では男性に比べ異常頻度が低いが、50歳代で異常が増え始め、特に高コレステロールは60歳以上の4割近くで異常がみられる。 人間ドックの受診者で健康度が改善しない理由として、日本人間ドック学会では「専門学会の基準に沿った判定基準が従来より厳しくなった」、「反復受診者の割合が7〜8割を占め、受診者の平均年齢が40歳代から50歳代へと移行した。60歳以上の受診者も増えた」等を指摘している。 「働き盛りの世代のリストラや経済のデフレ化などで社会環境が悪化している。ストレスが生活習慣の悪化につながっているおれそがある」、「脂肪のとりすぎなど日本人の食習慣が欧米化している。交通機関の発達などで歩行量が減り、運動不足をきたしている」等も一因となっている。 地域別の6項目合計平均値で「異常あり」がもっとも多かったのは九州・沖縄の29.6%。もっとも少なかったのは北海道の17.9%だった(全国平均は21.6%)。異常があった検査項目の最多は高コレステロールの26.5%で、肥満の26.3%、肝機能異常の25.8%が続いた。 人間ドックで発見されたがんの中でもっとも多かったのは胃がんで、みつかったがん全体の28%。1985年に全体の約6割を占めていた胃がんは年々割合が減少し、一方でその他のがんの占める割合が46%と増えている。女性では乳がんがトップで40.7%、男性は前立腺がんが胃がんに次いで13.8%を占めた。日本人間ドック学会 2009年「人間ドックの現況」(Terahata