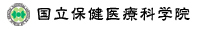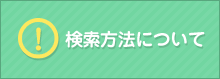病気の解説「前立腺癌」での検索結果

がんの臨床試験を探す- 国立がん研究センター -
上記以外...--> 上記以外のがんの領域を選択する場合はこちらから選択してください。 下垂体腺腫 聴神経鞘腫 ぶどう膜悪性黒色腫 髄膜腫 胸腺腫と胸腺がん 中皮腫 GIST --> 肝臓がん 胆のう・胆道がん 膵臓がん 上記以外...--> 泌尿器(腎細胞がん、膀胱がん、前立腺がんなど) 膀胱がん 前立腺がん--> 上記以外...--> 乳がん 子宮がん、卵巣がんなど 皮膚(悪性黒色腫、基底細胞がん

性機能障害とリハビリテーション(男性)- 国立がん研究センター -
に取り組んでいくことが大切です。 ・膀胱がん ・前立腺がん ・精巣(睾丸)腫瘍 よりよい情報提供を行うために、アンケートへの協力をお願いいたします。

ポジトロンCT(PET)検査Q&A- 国立がん研究センター -
で、これは写真で例えれば、ピントがずれたような画像のことです。したがって、 PETの画像だけでは異常が発見されてもピントが悪いために、「病気がどこにあるのか」ということがはっきりとわからない場合があります(後述の「臨床例」を参照してください)。この解決策として、PETの画像を評価する際には必ずCTやMRIといった、空間分解能の高い画像と対比させて診断することが重要となります。 また、FDGは炎症巣にも集積することが知られています。例えば、肺炎なども異常集積としてとらえられるので、がんとの区別が難しい場合があります。 さらに、PETでは診断が難しい、あるいはその有用性が低いがんがいくつか知られています。例えば、胃がん、腎がん、尿管がん、膀胱(ぼうこう)がん、前立腺がん、肝細胞がん、胆道がん、白血病等です。 ただし、これらのがんは「原発巣の診断には向かない」ということで、遠隔転移や再発診断にはPETが有効な場合もあります。 いずれにせよ、ある患者さんに対してPETが有用か有用でないかに関しては専門的な判断が必要ですので、一概に述べることは困難です。検査を受ける前に、専門医(放射線科医)へのご相談をお勧めします。 Q4PETの安全性は? A4PETで使用される薬剤はブドウ糖の一種で、副作用の報告はありません。毎日院内で合成、精製されますが、そのたびに専任の薬剤師が品質管理試験を行い、安全性を確認しています。 また、体内に投与されるアイソトープは量が少なく、半減期も非常に短い(半減期110分)ため、被曝量(ひばくりょう)は人体にほとんど影響のないごく微量です。およそ人間が1年間に自然界から受ける被曝線量と、ほぼ同じ程度とお考えください。 Q5検査は苦しくないの? A5検査はまず静脈注射をした後、薬剤が全身に分布するまで約1時間ほど待ちます。その後は、ポジトロンカメラのベッドに寝ているだけです。カメラはCTの装置に似ていますが、大きな音もせず、狭くもありません。撮影時間は30〜60分程度で、この間は安静にします(つまり、注射から検査終了まで約2時間かかります)。 なお、検査前の1食分(例えば、午後の検査であれば昼食)は食べられず、甘い飲料も摂取禁止ですからご注意ください。 PET検査を行なっている施設については、東北大学核薬学研究部ホームページ「PET関係

がんの種類から探す- 国立がん研究センター -
胆管がん 膵臓がん 膵神経内分泌腫瘍 腎・尿路/副腎 腎細胞がん 腎盂・尿管がん 膀胱がん 尿路上皮がん 副腎がん 褐色細胞腫 男性特有のがん 前立腺がん 精巣(睾丸)腫瘍 女性特有のがん 乳がん

転移性肺腫瘍- 日本呼吸器学会 -
なくなってもセツキシマブという薬があります。従来、肺に転移してしまうと有効な薬が少なかった腎がんや肝がんにも分子標的治療薬が開発されました。さらに前立腺がんなどの肺転移にはホルモン療法が非常に有効な場合があります。また、元の臓器のがんが切除されていて肺以外に再発がないこと、すべての転移巣が切除可能であることなど、いくつかの条件を満たせば手術が行われる場合もあります。結腸・直腸癌では、他の臓器に転移がなく、肺の一部を切除しても生活機能上特に支障がない場合は手術で取り除く方法がありますが、転移の個数や転移の場所、体力で慎重な判断が必要です。まずは、専門医にご相談ください。【治療費の軽減施策】 高額療養費制度により、高額ながん治療費を軽減できる施策があります。自己負担分が一定額以上になった場合、負担が軽減されます。詳しくは、各病院のがん相談センターまたは相談員にお尋ねください。【生活上の注意】 肺がんと同様、規則正しい食生活、感冒など感染に注意が必要です。 資料1

お酒を飲む人は「休肝日」を 厚生労働省研究班- 日本生活習慣病予防協会 -
があったという。 今回の研究結果について、研究に加わった丸亀知美・国立がんセンターがん情報・統計部研究員は、「この研究を含む多くの研究結果から、1日平均2合以上の多量飲酒は死亡のリスクが高くなるという結果が出ている。休肝日をもうけつつ、お酒はやはり1日平均で1合から2合程度にするほうがよいだろう。休肝日は、総飲酒量を減らすという観点からも重要」と話す。「お酒が心筋梗塞を予防」があてはまるのは、過度な飲酒を行わない人だけ またこのコホート研究では、適度な飲酒を続けている人では心筋梗塞の発症が減る傾向があることが日本人男性でも確かめられた。 調査は、1993年に茨城、新潟、高知、長崎、沖縄の5県に住んでいた40〜69歳の男性約2万3,000人に、飲酒習慣や顔が赤くなるかなどを尋ね、発症率を9年間追跡し調査した。 9年間に急性心筋梗塞になったのは170人。酒を飲まないグループの心筋梗塞のリスクを1とすると、1日に飲む量が「1合未満」、「1合から2合」のグループのリスクは、顔が赤くなるかどうかに関係なく0.5前後だった。その効果は、お酒で顔が赤くなる・ならないに関わらず認められたという。 アルコール飲料には善玉コレステロールと呼ばれるHDLコレステロールを増やす作用や、血液を固まりにくくする作用があると考えられており、欧米でも飲酒の心筋梗塞を予防する効果が報告されているが、今回の研究では、この効果がみられるのは過度な飲酒を行わない人のみで、飲酒量が増えると死亡率が高くなることが示された。厚生労働省研究班「多目的コホート研究(JPHC研究)」関連情報イソフラボンで前立腺がん抑制 進行段階では不明インスリンの過剰分泌で、大腸がんリスクが3.2倍に大腸がん予防に運動が有効(Terahata)◀ 前の記事

全国のがん罹患状況を公開 胃がんは日本海側に多い がん研究センター- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2015年05月08日全国のがん罹患状況を公開 胃がんは日本海側に多い がん研究センターキーワード:がん 国立がん研究センターは、主ながんの種類ごとに、がんのなりやすさを示す罹患状況を全国平均と比べた地域別の分析結果をはじめて発表した。 胃がんは日本海側で多い傾向があり、肺がんは北海道や近畿地方で多い傾向があり、肝臓がんは西日本が高いなどの特徴が明らかになった。 国立がん研究センターは、40の道府県から集めたがん患者のデータを解析。2011年にがんに罹患(新たにがんと診断されること)した全国推計値を算出し、7種類のがん罹患率の道府県別の値を算出した。全国平均は、特に精度が高い14県のデータから推計した。がん罹患率 男性1位は胃がん 女性1位は乳がん 2011年に新たにがんと診断されたのは男性49万6,304人、女性35万5,233人、合計85万1,537人だった。各部位の罹患数は、2010年の推計と比較し、男性では4位だった前立腺がんが2位に上昇した。女性では順位変動

1回の採血で13種類のがんを診断 次世代のがん診断技術を開発- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2014年09月19日1回の採血で13種類のがんを診断 次世代のがん診断技術を開発キーワード:がん 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)と国立がん研究センターなどは、血液から乳がんや大腸がんなど13種類のがんを早期発見する診断システムの開発をはじめると発表した。 国立がん研究センターによると、血液検査での早期発見を目指すのは、胃がん、食道がん、肺がん、肝臓がん、胆道がん、膵臓がん、大腸がん、卵巣がん、前立腺がん、膀胱がん、乳がん、肉腫、神経膠腫——の13種類。いずれも日本人の罹患者が多かったり、同センターが重点的に研究している疾患だ。 マイクロRNAとは、血液や唾液、尿などの体液に含まれる小さなRNAで、がんを発症すると血液中で種類や量が変動することが明らかになっている。さらに、こうした血液中のマイクロRNA量は、抗がん剤の感受性の変化や転移、がんの消失などの病態の変化に相関するため、全く新しい疾患マーカーとして期待されている。 研究では国立がん研究センターなどのバイオバンクに保存されている数十万検体の血清から、疾患の早期発見マーカーや、医療現場で必要とされるさまざまな疾患マーカーの探索を網羅的に行う予定だ。 日本人に多いがんの種類ごとに5,000人、計6万5,000人分の血液を解析し、がんの目印となるマイクロRNAを特定。数値を解析することで、がんの早期発見につなげる。 臨床現場で、体液(血清)中のマイクロRNAの抽出から検出までを全自動で、簡便・短時間に行える自動検査システムの開発を目指す。成功すれば、13種類のがん疾患や認知症の有無を1回の採血で診断できるようになる。 事業には、東レが開発した樹脂製のDNAチップを使用。東芝なども参加し、専用診断機器の開発を進めて産学官連携で、次世代のがん診断技術として開発

緑茶のがん予防効果:乳がんでは関連なし? 厚労省研究班- 日本生活習慣病予防協会 -
から10杯以上まで幅広く調べた研究は初めて」と述べている。 カテキン類の摂取量は、茶葉の種類・量、入れ方などの影響を受ける。研究にはカテキン類の摂取量の違いまで反映できていない可能性がある。しかし、1日10杯以上と非常に多く飲む女性でも乳がんリスクの低下はみられず、日常生活において飲用する範囲では乳がんリスクに関連しないことが示された」としている。 ただし、がんの部位別にみると緑茶は“予防効果がある”との結果も出ている。 JPHCスタディでは過去に、緑茶の胃がん予防効果についても調べており、緑茶をよく飲む40歳以上の女性では血中の緑茶ポリフェノール濃度が高く、胃がんのリスクが低下することが示されたが、喫煙習慣があるとこの効果を得られないという結果になった。また、40歳以上の男性では緑茶をよく飲んでいると、進行前立腺がんのリスクが低下するという結果が出ている。 研究は医学誌「Breast Cancer Research」に10月28日付けで発表された。Green tea drinking and subsequent risk of breast cancer in a population-based cohort of Japanese womenBreast Cancer Research 2010, 12:R88doi:10.1186/bcr2756独立行政法人 国立がん研究センター がん予防・検診研究センター 予防研究部(Terahata)◀ 前の記事へ次の記事へ ▶ 関連トピック 疾患 ▶ がん 2018年01月18日

難病情報センター間質性膀胱炎(ハンナ型)(指定難病226)- 難病情報センター -
。(注) 注)ハンナ病変とは、正常の毛細血管構造を欠く特有の発赤粘膜である。病理学的には、上皮はしばしば剥離し(糜爛)、粘膜下組織には血管の増生と炎症細胞の集簇がみられる。ハンナ病変はハンナ潰瘍又は単に潰瘍と称されることもある。 注)膀胱拡張術後の点状出血を認める場合も間質性膀胱炎と診断されるが、今回対象となるハンナ型とは異なり間質性膀胱炎(非ハンナ型)と分類される。膀胱拡張術後の点状出血とは、膀胱を約80cm水柱圧で拡張し、その後に内容液を排出する際に見られる膀胱粘膜からの点状の出血である。 C.鑑別診断 上記の症状や所見を説明できる他の疾患や状態がない。(注) 注)類似の症状を呈する疾患や状態は多数あるので、それらを鑑別する。例えば、過活動膀胱、膀胱癌、細菌性膀胱炎、放射線性膀胱炎、結核性膀胱炎、薬剤性膀胱炎、膀胱結石、前立腺肥大症、前立腺癌、前立腺炎、尿道狭窄、尿道憩室、尿道炎、下部尿管結石、子宮内膜症、膣炎、神経性頻尿、多尿などである。 <診断のカテゴリー> Definite:A、B、Cの全てを満たすもの。 上記B.検査所見で以下の2型に分類し、間質性膀胱炎(ハンナ型)を対象とする。(注) ①間質性膀胱炎(ハンナ型):ハンナ病変を有するもの。 ②間質性膀胱炎(非ハンナ型):ハンナ病変はないが膀胱拡張術時の点状出血を有するもの。 注)①の患者の方が高齢で症状も重症で、病理学な炎症所見が強い。治療方法も異なるので、この2者の鑑別は重要である。 <重症度分類> 日本間質性膀胱炎研究会作成の重症度基準を用いて重症を対象とする。 重症度 基 準 重症 膀胱痛の程度*が7点から10点 かつ 排尿記録による最大一回排尿量が100mL以下 中等症