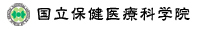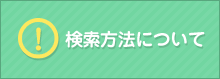病気の解説「前立腺癌」での検索結果

がんの手術前後のリハビリテーション- 国立がん研究センター -
性機能障害とリハビリテーション(女性) リンパ浮腫 8.泌尿器がん手術に対するリハビリ 泌尿器がんには、膀胱(ぼうこう)がん、腎盂(じんう)・尿管がん、前立腺がん、腎細胞がん、精巣(睾丸)腫瘍などがあり、これらの手術の影響により、排尿障害、性機能障害、むくみがもたらされる場合があります。手術後に排尿リハビリテーションが必要となる代表的なものは、膀胱がんで膀胱を摘出した場合と、前立腺がんで前立腺を摘出した場合の2つです。 ●膀胱がん、前立腺がん 膀胱を摘出した場合のリハビリテーション 前立腺を摘出した場合のリハビリテーション 性機能障害とリハビリテーション(男性) リンパ浮腫 9.四肢、骨などの手術に対するリハビリ 悪性骨軟部腫瘍では、がんになった周囲の筋肉の集まりを広範囲に切除する場合があります。疼痛(とうつう)、運動障害

原発不明がん (治療の選択)- 国立がん研究センター -
ます。 腺がんと診断され、原発部位特定の可能性が高そうな以下の(1)~(3)の場合には、それぞれに準じた治療が行われます。 一方で、腺がんと診断はされたものの、原発部位特定が難しい場合は標準治療とされるものはありません。また多くは病期がすでに進んで(がんが広がって)いるため、手術(外科治療)や放射線治療で治すことはできません。がんそのものに対する治療としては、抗がん剤を使ってがんの進行を抑える治療を行うのも選択肢の1つです。しかし、治療をしたとしても効果は限られるため、抗がん剤の副作用の負担を考えて、あえて治療せずに注意深く経過観察しながら緩和ケアを行うということも選択肢としてあり、体とがんの状態に応じて検討します。その緩和ケアの一環として手術(外科治療)や放射線治療を行うこともあります。また状況によっては臨床試験なども考えられます。 (1)わきの下のリンパ節(腋窩[えきか]リンパ節)の腫(は)れのみで診断された女性の腺がんの場合 詳しい病理検査や腫瘍マーカーの結果などによって、乳がんの可能性が最も高い場合は、多くは乳がんに準じた治療として、手術(外科治療)や放射線治療、抗がん剤による化学療法や、組織型によってはホルモン療法(抗エストロゲン療法)を行います(参照:「乳がん 治療」)。 (2)腹水の存在のみで診断された女性の腺がんの場合 消化器がん(胃がん、大腸がん、膵臓がん、胆道がんなど)の転移で腹膜播種(はしゅ)の場合もありますが、腫瘍マーカーであるCA125が高値を示し、詳しい病理検査などで卵巣がんの可能性が最も高い場合、婦人科医による十分な検査や腹部骨盤CTなどで卵巣に異常がなくても、多くは卵巣がんに準じて手術(外科治療)や抗がん剤による化学療法を行います(参照:「卵巣がん 治療」)。 (3)骨への転移のみで診断された男性の腺がんの場合 腫瘍マーカーであるPSAが高値(特に10ng/mL以上)を示す場合には前立腺がんが強く疑われます。前立腺生検もしくは骨生検による詳しい病理検査で診断が得られれば、前立腺がんに従った標準治療を行いますが、診断が得られない場合でも前立腺がんに準じてホルモン療法(抗アンドロゲン療法)、化学療法を行うことがあります(参照:「前立腺がん 治療

がん外来患者の4割は「初診時に自覚症状なし」- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2013年03月18日がん外来患者の4割は「初診時に自覚症状なし」キーワード:がん がんや糖尿病は初期の段階では自覚症状が乏しいために、健康診断を受けずにいると、早期に発見できず治療が遅れることがある。実際に、自覚症状などにほとんど気付かなかった人が、健康診断や人間ドックを受診した際に、再検査を指摘され、病気が発見される例は多い。 厚生労働省の調査で、外来患者が受診し症状をはじめて医師に診てもらったときに、4人に1人は受診の時点で「自覚症状がなかった」ことが分かった。 調査は、全国500病院を対象に2011年10月に実施した「受療行動調査」の結果のうち、病名が分かる外来患者3万1,795人の回答を分析したもの。 それによると、外来患者が受診した病気や症状を初めて医師に診てもらった時、「自覚症状があった」は59.0%、「自覚症状がなかった」は24.7%だった。 「自覚症状があった」と回答した者の最初の受診場所をみると、「今日来院した病院」が49.1%、「他の病院」が29.8%、「診療所・クリニック・医院」が17.2%だった。 「自覚症状がなかった」と回答した者の受診した理由をみると、「健康診断(人間ドック含む)で指摘された」が37.1%、「他の医療機関等で受診を勧められた」が20.0%、「病気ではないかと不安に思った」が12.9%だった。 がんに限ってみると、がんと診断された外来患者のうち41.5%が「自覚症状がなかった」と回答。自覚症状がないのに受診した理由は「健康診断や人間ドックで(詳しい検査を受けるよう)指摘された」が最多だった。 がんの部位別で自覚症状がなかった人の割合は、胃がん49.9%、結腸・直腸がん38.9%、肝・肝内胆管42.9%、気管・気管支・肺がん54.9%、乳がん37.2%、前立腺がん53.8%となっている。 糖尿病については、外来患者のうち40.0%が「自覚症状がなかった」と回答、「自覚症状があった」は40.9%だった。 厚労省の担当者は「生活習慣病の基本は早期発見。自主的に健康診断

健診+温泉でゆったり 日光の旅館組合が医大センターと提携- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2011年02月09日健診+温泉でゆったり 日光の旅館組合が医大センターと提携キーワード:健診・保健指導 日光市の鬼怒川・川治温泉旅館協同組合は、独協医科大学日光医療センターと提携し、3月31日までの限定で温泉ホテル・旅館に泊まりながら検査を受けられる「きぬ姫健診プラン」を始めた。今後も健診項目を変えるなどして実施を重ね、観光と医療を結び付けた新たなサービスでリピーター客の獲得につなげたい考え。 日光周辺には世界遺産に登録された社寺を含む日光国立公園をはじめ、鬼怒川、川治、塩原などの著名な温泉郷がある。独協医大日光医療センターでで実施する人間ドックは、鬼怒川の温泉地で宿泊・食事し、温泉を健康増進やリフレッシュにも役立てられるのが特色となっている。 今回のプランの健診では、女性は乳がんを発見する超音波検査(乳房)、子宮頸がんを発見する子宮頚部細胞診の検査を、男性は前立腺がんの有無を調べる血液腫瘍マーカー、動脈硬化の進行や脳梗塞の危険性を調べる頚動脈超音波検査を受けられる。 組合加盟のうち14軒のホテル・旅館に泊まりながら、期間中の祝日を除く平日に利用できる。検査時間は約2時間半。申込み健診の2週間前までに、宿泊旅館・ホテルを通じて受け付ける。健診費用は2万1000円で、宿泊込みの人間ドックに比べ気軽に受診できる料金に設定した。 成長分野として注目されている医療ツーリズムは、「医療を受ける目的で外国へ渡航すること」というのほかに、観光・療養地の資源を医療や関連産業の活用化にも活用するという意味合いも含まれる。同医療センターは「観光医療科」を開設し、昨年10月には「国際観光医療学会」(寺野彰理事長)の第1回学術集会が日光東照宮の客殿・社務所で開催された。 同組合では「自然に恵まれた鬼怒川・川治温泉を利用しながら健康診断と観光の両方で満足してもらいたい」と期待している。「きぬ姫健診プラン」に関する連絡先きぬ姫まつり実行委員会(鬼怒川・川治温泉旅館協同組合)Tel 0288-77-1039

原発不明がん (治療)- 国立がん研究センター -
します。 3.薬物療法 主に、限られた範囲にとどまっているがんを標的とした手術や放射線治療の局所療法ができないほど、がんが広がった場合には、抗がん剤による化学療法を行います。また疑われる原発部位にもよりますが、局所治療が可能な病期でも、術後の再発や遠隔転移の予防のために、術前あるいは術後に薬物療法が追加されることもあります。乳がんや前立腺がんの可能性が最も高い場合は、ホルモン療法(乳がんでは抗エストロゲン療法、前立腺がんでは抗アンドロゲン療法)を行います。 ●抗がん剤の副作用 抗がん剤は、がん細胞だけでなく正常な細胞にも影響を及ぼします。特に髪の毛、口や消化管などの粘膜や骨髄など新陳代謝の盛んな細胞が影響を受けやすく、脱毛、口内炎、下痢、白血球

原発不明がん (検査・診断)- 国立がん研究センター -
されません。その一方で、胚細胞腫瘍、甲状腺(こうじょうせん)がん、前立腺がん、卵巣がんという限られたがん種の検索には腫瘍マーカーも有用です。胚細胞腫瘍ではAFPやβ-hCG、前立腺がんではPSA、卵巣がんではCA125、甲状腺がんではTg(サイログロブリン)が対応する腫瘍マーカーになります。 【参考文献】 日本臨床腫瘍学会編:原発不明がん診療ガイドライン2010年版;メディカルレビュー社 閉じる 基礎知識診療の流れ検査・診断治療の選択治療生活と療養転移・再発 全ページ表示 【がんになったら手にとるガイド】 ・がんと言われたとき

ひとつかみの「くるみ」が健康の切り札 研究が進む「くるみ」の魅力とは?- 日本生活習慣病予防協会 -
・クリニックのエミリオ・ロス氏は「PREDIMED試験:心血管リスク削減の状況を変える」と題し講演し、「炎症反応によるダメージが繰り返されるとやがて動脈硬化の原因となり、これが心臓疾患につながると考えられます。最新の研究でくるみの摂取により血管機能が改善されることが判明しました」(※4)と述べました。 スペインで行われた心血管疾患と地中海食に関する大規模な臨床試験「PREDIMED」により、くるみなどのナッツ類を食べる習慣が、心血管疾患とがんのリスク減少との関連性が高いという研究結果が発表されました。PREDIMEDは、心血管系疾患の一次予防における地中海食の効果を調べることを目的とした研究で、スペインの7地域で16の研究グループによって行われました。 くるみを中心としたナッツ類を加えた地中海食群では、低脂肪食に関する指導を行った対照群と比べ、心血管系疾患(心筋梗塞、脳卒中、心血管系死亡)のリスクが30%抑制され、脳卒中に限るとリスクが49%抑制されました。くるみを積極的に食べる地中海食に心臓病、脳卒中などの心血管疾患に対する予防効果があることはこれまでに行われた複数の研究結果によって報告されていますが、「PREDIMED」の結果によりあらためてその関連性が示されました(※5)。日本人の“くるみ”の摂取と生活習慣病との関連を調査 国立循環器病研究センター予防検診部医長の小久保喜弘氏は「日本の心疾患、メタボリックシンドロームの状況 日本の食事パターンについて」と題して講演しました。日本人を対象とした疫学研究により、動脈硬化や冠動脈性心疾患を予防するために、禁煙、節酒、運動習慣、バランスのとれた食生活などの生活習慣が効果的であることが確かめられています(※6)。特に喫煙に関しては、禁煙後数年で心疾患の発症リスクが低下することから、年齢に関係なく禁煙することが大切となります。食生活では、魚と大豆、野菜、果物、乳製品をバランスよく摂取すること、ナトリウム摂取量を減らすことが循環器疾患を予防するために大切となります。 「くるみや魚などのオメガ3(n-3系)脂肪酸が含まれる食品には、動脈硬化を改善したり心血管疾患などを予防する作用があることが確かめられています。一方で日本人を対象としたくるみに関する研究は少なく、くるみをどのように摂取したら良いかが課題になっています。今後は日本人のくるみの摂取と生活習慣病との関連を調査する必要があります」と、小久保氏は述べました。 コネチカット大学分子細胞生物学准教授のチャールズ・ジャルディーナ氏は「がん予防に向けた食事勧告の根拠となるエビデンス」と題し講演し、くるみを1日2オンス(56グラム)食べると前立腺がんの発生と進行を防ぐことを示した研究を紹介しました。テキサス大学保健科学センターサンアントニオの研究者らによる研究で、くるみを加えない食事を与えられた対照群マウスでは前立腺がんの腫瘍の発生率が44%だったのに対し、くるみを加えた食事を与えられた実験群マウスでは18%に抑えらました。がんの発生

それぞれのがんの解説 (部位・臓器別)- 国立がん研究センター -
) GIST 肝臓・胆のう・膵臓 肝細胞がん 胆管がん 胆のうがん 膵臓がん 泌尿器 腎細胞がん 腎盂・尿管がん 膀胱がん 男性特有のがん 前立腺がん 精巣(睾丸)腫瘍

尿1ミリリットルで「がん診断」 簡単な検査でがんを早期発見- 日本生活習慣病予防協会 -
した。尿を使えばがん検査はより簡単になる さらに、がん患者の尿と健常者の尿から採取したマイクロRNAを比較し、がん患者で特異的に過剰に発現または減少するマイクロRNAを発見した。こうして、泌尿器系のがん(前立腺・膀胱)のみでなく、非泌尿器系のがん患者(肺・膵臓・肝臓)でも、がん患者に特異的にあるマイクロRNAを発見することができた。 肺、膵臓、肝臓、膀胱、前立腺のがん患者と健康な人、それぞれ3人ずつの尿を調べ、それぞれのがんに特有のマイクロRNAを特定するのに成功した。今回開発した技術を活用すれば、尿を使い、体を傷つけない(非侵襲)新たながん診断法を開発できる可能性がある。 がん研究センターは、これまでに血液1滴から13種類のがんのマイクロRNAを調べる検査法も開発しているが、尿を使えば検査がより簡単になる。 研究は、名古屋大学の馬場嘉信教授、安井隆雄助教らが、九州大学、国立がん研究センター研究所、大阪大学と共同で行ったもので、科学誌「Science Advances」に発表された。国立がん研究センター研究所Unveiling massive numbers of cancer-related urinary-microRNA candidates via nanowires(Science Advances 2017年12月15日)(Terahata)◀ 前の記事へ次の記事へ ▶ 関連トピック 疾患 ▶ がん

人間ドックで「異常なし」が過去最低に 人間ドック学会- 日本生活習慣病予防協会 -
代では10.8%(前年比1.7ポイント減)、50歳代では6.3%(前年比1.2ポイント減)、60歳以上では4.6%(前年比1.1ポイント減)となった。 異常なしの割合は調査を始めた1984年の29.8%がもっとも高く、2006年には11.4%まで低下していた。2007年の調査では初めて増加に転じ、下げ止まりが期待されていたが、再び減少した。生活習慣病と関連の深い6項目を年齢層別にみると、なんらかの異常が認められた人の割合は中性脂肪を除いては総ての項目で前年より増加した。 異常が認められた項目で、もっとも高いのは「高コレステロール」(26.4%)で、以下は「肝機能異常」(26.2%)、「肥満」(26.1%)、「高血圧」(17.7%)、「耐糖能異常」(16.3%)、「高中性脂肪」(14.6%)と続く。 性別にみると、男性では「肝機能異常」(31.9%)が高く、次いで「肥満」(30.6%)、「高コレステロール」(26.6%)、「高血圧」(20.9%)、「耐糖能異常」(19.6%)、「高中性脂肪」(18.8%)と続く。6項目異常頻度(男性・年代別)50歳代・男性では肝機能異常、肥満、高コレステロールの異常の頻度が高くなり、耐糖能異常と高血圧は年齢が高くなるほど上昇する。日本人間ドック学会、日本病院会「人間ドックの現況(平成20年度調査)」 人間ドックで発見されるがんのトップは胃がんで、次いで大腸がん。両方を合せると20年前は全がんの約70%を占めていたが、今回の調査では約47%と減少傾向を示している。学会は「その他のがんが年々増加し、特に男性では前立腺がん、女性では乳がんが著しく増えたため」としている。 年代別に比べると、肝機能異常、肥満、高中性脂肪、高コレステロールは50歳代をピークとして60歳以上は下降傾向を示しており、高血圧と耐糖能異常は加齢とともに上昇傾向を示している。異常なしが減少した原因として、日本人間ドック学会は「受診者の平均年齢が40歳代から50歳代へと移行し、さらに60歳以上の受診者が年々増加している。職場環境、家庭環境などの生活環境が変化している影響もある。メタボリックシンドロームは環境悪化に基づく生活環境病であると認識し、総合的な対策を立てる必要がある」と説明している。メタボリックシンドロームは環境悪化に基づく生活環境病一般社団法人日本人間ドック学会