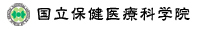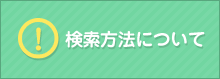病気の解説「前立腺癌」での検索結果

代替療法(健康食品やサプリメント)- 国立がん研究センター -
容認して経過観察 前立腺がんに対する脂肪制限 II-2 → 1 N 容認して経過観察 マクロバイオティック食(野菜や玄米中心の食事) III → 2 E, N 容認して経過観察 ビタミンAサプリメント I → 6 A, T 反対して経過観察 ビタミンCサプリメント

大豆の栄養パワーを再評価 大豆は自然のバランス栄養食- 日本生活習慣病予防協会 -
を低く調整することができる。結果的に低脂肪、低カロリーのメニューを実現できる。・ カルシウム 豆腐にはカルシウムが豊富に含まれている。100g当りに含まれるカルシウムの量は牛乳より豆腐の方が多い。牛乳コップ1杯(200ml)で約200mgのカルシウムを取ることができるが、豆腐半丁(150g)では約180mgのカルシウムをとることができる。 また、豆腐は消化吸収が良く、さらに良質のタンパク質と一緒にとることもできるので、カルシウムの摂取に有用な食品だ。 食事摂取基準では1日に約600mgのカルシウムを食品でとる必要があるとされているが、男性で14%、女性で18%も不足しているのが現状だ。これを補うのに必要な量を逆算した場合、1日に豆腐を3分の1丁(カルシウム90mgを含有)を食べれば良いことになる。・ 食物繊維 大豆といえばタンパク質やイソフラボンなどが注目されることが多く、食物繊維が多いという印象は薄いかもしれない。実際には大豆に含まれる食物繊維は、きのこ類や野菜類に比べても多い。 例えば食物繊維が多い野菜として知られるゴボウには100gあたり6.1mgの食物繊維が含まれている。大豆にはゴボウの約3倍の17.1mgの食物繊維が含まれている。・ イソフラボン イソフラボンは、大豆胚芽に含まれるフラボノイドの一種で、女性ホルモン(エストロゲン)によく似た構造をしている。そのため「植物エストロゲン」の異名があるが、その作用は女性ホルモンの1000分の1程度とおだやかだ。 大豆に含まれるイソフラボンには、コレステロールを下げるのに効果がある。イソフラボンは豆腐半丁に40mg、納豆1パックに35mg、豆乳1パックに40mg含まれている。国立健康・栄養研究所の調査で、大豆イソフラボンを1日100mg、1〜3ヵ月間摂取すると、血中総コレステロールと「悪玉コレステロール」とされているLDLコレステロールがそれぞれ平均3.9mg/dL、5.0mg/dL低下することが確認された。 また、大豆を食べる人ほど、がんの発症が少なく、イソフラボンが予防効果をもつことを示した研究は多く発表されている。国立がん研究センターが40〜59歳の女性約2万人を対象とした調査で、大豆、豆腐、油揚、納豆を毎日食べる女性では、乳がんの発症率が2割減ることが明らかになった。 閉経後の女性に限ると、イソフラボンをたくさん食べれば食べるほど、乳がんなりにくい傾向がより強まった。イソフラボンの摂取量が最大の女性では、最小の女性に比べ、乳がんの発症が半数以下に減っていた。 これ以外にも、大豆に含まれる脂肪酸のリノール酸やリノレン酸、レシチンには、抗酸化作用(活性酸素を抑え、体の老化・酸化を防ぐ作用)があり、また豆腐などの苦味成分であるサポニンにも抗酸化作用があるとみられている。中高年の男性にも大豆食品はお勧め 「植物エストロゲン」と聞くと、「イソフラボンが女性の健康に効果的なのは知っているが、男性ではどうなのか」という疑問を感じる人も多いだろう。国立がん研究センターの調査が約4万3,000人を対象とした調査では、大豆をよく食べている61歳以上の男性では、摂取量がもっとも多いグループで、もっとも少ないグループと比べ、前立腺がんの発症

がん患者数が最多の86万人 罹患率に地域差 自治体の取組みが影響- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2016年07月07日がん患者数が最多の86万人 罹患率に地域差 自治体の取組みが影響キーワード:がん 2012年の1年間に新たにがんと診断された患者は86万5,238人だったとの推計値を、国立がん研究センターがまとめた。前年より約1万4,000人増加し、過去最多となった。全都道府県比較により、がん罹患率には地域差があることもはっきりした。男性1位は「胃がん」 女性1位は「乳房がん」 国立がん研究センターは、全国の病院から報告を受け、各都道府県が「地域がん登録」として集計したがん患者データを基に全国の患者数を推計した。 その結果、2012年の新規の患者数は男性が50万3,970人、女性は36万1,268人だった。 部位別にみると、男性では(1)胃がん、(2)大腸がん、(3)肺がん、(4)前立腺がん、(5)肝臓がんの順で多く、女性は(1)乳房がん、(2)大腸がん、(3)胃がん、(4)肺がん、(5)子宮がんの順だった。男性では前立腺がんの増加が頭打ちになり、大腸がんが増加しているという。 「地域がん登録」は、都道府県のがん対策を目的に1950年代より一部の県で開始され、研究班が各地域がん登録からデータを収集する活動を開始して以降、年々参加都道府県が増加し、2010年は30県、2011年は40県、そして今回はじめて47全都道府県の登録データが揃った。がん罹患率に地域差 40歳代後半から罹患率は増加 データから高齢化の影響を除くと、人口10万人当たりの患者数(年齢調整罹患率)は男性447.8人、女性305.0人で男女合計は365.6人。前年より0

がん未承認薬を使った「混合診療」 月100万円以上の高額負担に懸念の声- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2015年05月24日がん未承認薬を使った「混合診療」 月100万円以上の高額負担に懸念の声キーワード:がん 国立がん研究センターは、国内未承認薬を混合診療として使えるようにする「患者申出療養」(仮称)の対象となる抗がん剤が、1月末時点で42種類に上るとの集計結果を発表した。 うち24種は薬剤費が円換算で月に100万円を超えることも判明し、承認されて公的医療保険が適用されないと、患者の負担が高額になることが明らかになった。未承認薬剤を使った混合診療を認める「患者申出療養」 「患者申出療養」(仮称)とは、患者が希望すれば、迅速な審査で国内未承認の薬剤を使った医療を混合診療として認めるという制度(保険外併用療養費制度)。今国会で審議され、2016年度に導入される見込みだ。 「混合診療」では、公的医療保険で認められている保険診療と保険外の診療を併用することを原則として禁止されているが、この制度では、未承認薬・適応外薬の薬剤費を患者の自己負担で使えるようになる。 国立がん研究センター先進医療評価室が公開した「国内で薬事法上未承認・適応外となる医薬品・適応のリスト」によると、1月末時点で欧米既承認・日本未承認の抗がん剤は42剤に上る。未承認抗がん剤の薬剤費は1ヵ月当たり100万円以上 患者申出療養の対象となるのは、血液がん、悪性黒色腫(メラノーマ)、前立腺がんなどで、これらの抗がん剤の大半は1ヵ月当たり100万円以上の薬剤費が必要となる。 その内訳をみると、主な抗がん剤は、悪性リンパ腫など血液領域が19剤、メラノーマなど皮膚科領域が5剤、前立腺がんなど泌尿器科領域が5剤、骨軟部腫瘍が2剤、甲状腺がんが2剤、非小細胞肺がんなど肺がんが2剤だった。5大がんとされる胃がん、大腸がん

がんと新たに診断されるのは98万人と予測 国立がん研究センター- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2015年06月15日がんと新たに診断されるのは98万人と予測 国立がん研究センターキーワード:二少(少食・少酒) がん 「無煙」喫煙は万病の元 三多(多動・多休・多接) 国立がん研究センター(国がん)は、2015年に新たにがんと診断される患者の数(罹患数)と死亡数の予測を発表した。高齢化やがん登録精度の向上などを背景に、予測がん罹患数は98万例になり、前年より10万例増加した。がん罹患数 高齢化で「大腸」1位に 予測がん罹患数(新たにがんと診断されるがんの数)は98万2,100例(男性56万300例、女性42万1,800例)で、2014年予測値より約10万例増加、実測値に近い2011年度推計から約13万例増加となった。 罹患数が多いのは全体では大腸がん(13万5,800例)、肺がん(13万3,500例)、胃がん(13万3,000例)、前立腺がん(9万8,400例)、乳がん(女性、8万9400例)。 また、がんによる死亡数は37万900人(男性21万9,200人、女性15万1,700人)と、2014年予測値より約4,000人の増加した。 死亡数は肺がん(7万7,200人)、大腸がん(5万600人)、胃がん(4万9,400人)、膵臓がん(3万2,800人)、肝臓がん(2万8,900人)の順に死亡数が多かった。大腸がんが胃がんを抜いて2番目

大豆は世界でも注目の健康食品 日本食が良い理由は「大豆を食べるから」- 日本生活習慣病予防協会 -
れている。 国立健康・栄養研究所の調査で、大豆イソフラボンを1日100mg、1~3ヵ月間摂取すると、血中総コレステロールと「悪玉コレステロール」とされているLDLコレステロールがそれぞれ平均3.9mg/dL、5.0mg/dL低下することが確認された。 また、大豆を食べる人ほど、がんの発症が少なく、イソフラボンが予防効果をもつことを示した研究は多く発表されている。国立がん研究センターが40~59歳の女性約2万人を対象とした調査で、大豆、豆腐、油揚、納豆を毎日食べる女性では、乳がんの発症率が2割減ることが明らかになった。 閉経後の女性に限ると、イソフラボンをたくさん食べれば食べるほど、乳がんなりにくい傾向がより強まった。閉経後の女性でイソフラボンの血中濃度が高いと、乳がんの発症が半数以下に減っていた。 これ以外にも、大豆に含まれる脂肪酸のリノール酸やリノレン酸、レシチンには、抗酸化作用(活性酸素を抑え、体の老化・酸化を防ぐ作用)があり、また豆腐などの苦味成分であるサポニンにも抗酸化作用があるとみられている。 中高年の男性にも大豆食品はお勧め 「植物エストロゲン」と聞くと、「イソフラボンが女性の健康に効果的なのは知っているが、男性ではどうなのか」という疑問を感じる人も多いだろう。国立がん研究センターの調査が約4万3,000人を対象とした調査では、大豆をよく食べている61歳以上の男性では、摂取量がもっとも多いグループで、もっとも少ないグループと比べ、前立腺がんの発症が半分に減るという結果が出た。 男性の前立腺では、治療の必要がない微少ながんが加齢と共に増加することが知られている。日本人でもがんに進行して臨床的に発見される例が増えているが、欧米人に比べると少ない。「大豆を日常的に食べる」食生活が定着しているからではないかと指摘されている。 前立腺がんは、男性ホルモンの働きが影響し発症するがんだが、女性ホルモンに似た作用をもつイソフラボンをとっていると、男性ホルモンの過剰な働きを抑え、前立腺がんができにくく、できても進行が抑制されると考えられている。 大豆を食べると体重を減らせリバウンドも抑えられる 国連食糧農業機関(FAO)は、2016年を「国際豆年」に定め、体に良い大豆などの豆類を食べることを奨励している。大豆などの豆類を食べると、体重を適正に維持するのに役立つことが明らかになった。豆類を1日あたり130g食べていると、0.34kgの減量につながるという。 「グリセミック指数」(GI)は、ブドウ糖を摂取した後の血糖上昇率を100として、それを基準に、同量摂取したときの食品ごとの血糖上昇率をパーセントで表した指標。GI値が低い食品ほど食後の血糖値を上げにくくなる。 大豆は代表的な低GIの食品

弁置換後のワーファリン服用と手術時の注意- 日本心臓財団 -
15年前に弁膜症手術を受け、その後、ワーファリン、パラミジン、ブロプレス、ヘルベッサーを服用しています。最近、前立腺肥大症でハルナールを飲み始めましたが、現在、前立腺肥大の手術をすすめられています。ただ、手術前後一週間はワーファリンを止めることで、血栓のリスクが高くなるとも言われました。何かよい方法はありますか。お尋ねの件は、記述内容が簡単なので、具体的に指示を書くことはできません。そこで先ず、この方のように弁膜症の手術を受けて、ワーファリンとパラミジンを服用しておられる方とそのご家族が十分理解しておかれるべき一般的なこと(これは恐らく既にご存知であろうとは思いますが)を(1)と(2)に書いて、その後に何故この方が難しいかの理由と、この方に対する私の簡単な意見を書いておきます。 (1)弁膜症の手術(どのような人工弁をいくつ使ったかわかりませんので)を受けられてから15年経って調子の悪くない方で、ワーファリンとパラミジンを続けて内服している人は、一般に出血も血栓も生じやすい状態なので、平静から定期的に(2週?1ヶ月に1回以上)血液の固まりやすさを調べる検査(PT-INRやトロンボテスト)と出血のないこと(鼻血、歯ぐき出血、尿や便への出血)を確かめておくことが必要で、この方も地域の専門医に通院しておられるはずです。外傷や手術の際には、前後特別の注意を払わなければなりません。特に頭を打ったあとの硬膜下血腫など内出血も起こり易いので、医師と繰り返し相談すべきです。内出血の起こりやすい処置(例えば内視鏡生検や眼科の手術、脊椎の手術など)には周りの人も含めて慎重な行動が望まれます。またワーファリンの量は、検査値の変化があった時には、主治医から必要に応じた指示を受けなければなりません。パラミジンなどと併用している時には、そのことによってワーファリンの効果の持続時間が少し変わります。怪我や出血の起こらないよう周りの人達も注意してあげてください。血圧が高い人はさらに厳重な注意が必要で、この方も降圧剤を服用しておられることからこの枠に入ります。(2)その他の薬(例えば抗血栓薬や止血薬など血液の固まり方を変化させる薬、ヘパリン、トロンビン、ビタミンK、イプシロン、抗菌薬、解熱薬、鎮痛薬など)の注射や内服を併用する時には、主治医と十分相談して、検査を受けながら、ワーファリンの量を調節してもらわなければなりません。また食事についても、納豆やクロレラなどを食べる時はいつも一定の量を食べるようにしてください。このようなビタミンKの吸収されやすい食物をとる人が、一度にたくさん食べると血液の固まり方は大きく変化します。ワーファリンの効果について詳細に知っている主治医に、併用薬や食事について十分説明してもらってください。(3)この患者さんは、既に15年以上ワーファリンとパラミジンを服用しておられるので、(1)、(2)で述べたことはよくわかっている筈ですが、どんな人工弁をつけてもらっているのかが書かれていませんでしたし、心不全になったことがあるのかどうか、肝機能は大丈夫なのか、また心房細動があるかどうかも書かれていないので、症状に応じたワーファリンの服用の仕方について何も助言できません。しかも降圧薬(ブロプレスとヘルベッサー)を服用していて血圧はどうなっているのかもわかりません。前立腺肥大の手術を受けるとのことですが、どの程度の症状か、ハルナールだけではだめなのか、その他の薬も試みたのか、肥大があっても生命には関わらないので手術しないで辛抱できないのか。前立腺がんでなければ手術

牛乳を飲む人で心臓病などの死亡リスクが低下- 日本生活習慣病予防協会 -
ホーム 最近の関連情報・ニュース 最近の関連情報・ニュース 2009年07月23日牛乳を飲む人で心臓病などの死亡リスクが低下キーワード:心筋梗塞/狭心症 脳梗塞/脳出血 がん 健康食品 牛乳をよく飲む人では冠動脈性心疾患(CHD)などの死亡危険が最大で15-20%低下するという知見が欧州で発表された。 英国カーディフ大学のピーター エルウッド教授と英国レディング大学のイアン ギブンズ教授らは、食品の連鎖と健康との関わりを調査するために、牛乳の摂取に関する324の研究を調査し、CHD、脳卒中、糖尿病、がんなどの慢性疾患との関連を検証した。 「牛乳の摂取とCHDや脳卒中、結腸直腸がんによる死亡は関連があることが示された」とギブンズ教授は述べている。「冠動脈性心疾患、心臓発作、結腸直腸がんの死者数を考慮したところ、こうした病気による死亡リスクは牛乳の摂取により有意に低下した」。 牛乳やヨーグルトといった乳製品には蛋白質やカルシウム、ビタミンD、カリウムなどに加え、糖質や飽和脂肪酸も含まれる。乳製品を多くとりすぎると、前立腺がんになる危険が高くなる可能性があると指摘されている。また、乳製品などから飽和脂肪酸をとりすぎると、動脈硬化が起こりやすくなることも知られており、「不健康な食品」とされている風潮がある。 この点について研究者らは、「前立腺がんを例外として、牛乳を飲む

ビタミン剤を飲むとがんの発症が減る 1.5万人を調査- 日本生活習慣病予防協会 -
だった。二重盲検プラセボ比較試験として行われ、参加者は総合ビタミン剤を毎日飲む群と偽薬(プラセボ)を飲む群に無作為に分けられた。 平均11.2年の期間中に2,669人ががんと診断され、1,373例が前立腺がんで、210例が結腸・直腸がんだった。 解析した結果、総合ビタミン剤を飲んでいた群の方が、がんの発症が8%低下したことが分かった。前立腺がんでは影響をみられなかったが、それ以外の結腸、直腸、肺、そして膀胱などは、総合ビタミン剤を飲んでいた群で低下していた。 ただし、総合ビタミン剤を摂取することでどの部位のがんを予防できるか、詳しくことは分かっていない。また、女性や喫煙者において、がん予防効果があるかどうかも不明のままだ。研究の対象となったのは、医師を含む健康な医療従事者で、喫煙習慣をもたず、肥満や過体重も少なかった。 研究が1997年に始められた頃は、保健専門家のほとんどはビタミンのサプリメントは健康に有益だろうと考えていた。しかしその後、特定の栄養素を過剰に摂取すると、むしろ体にとって害になることもあることが示され、サプリメント類の摂取はむやみに勧められないことが知られるようになった。今回の研究ほど大規模なものではないにしても、ビタミン剤の摂取はがんの発症を特に減らすわけではないとの研究も発表されている。 「総合ビタミン剤をとる主な理由は不足している栄養素を補うことだ。今回の研究は、中高年者においてはがんの予防の観点で、総合ビタミン剤の服用が勧められるという結果になった。ビタミン剤で特定の栄養素を過剰に摂取するよりも、各栄養素をバランス良くとったほうが効果がある可能性がある。それを確かめるためにはさらなる研究が必要だ」とGaziano氏は述べている。「ただし、がんを予防するために全ての人に勧められるのは、禁煙と運動を習慣として行うことだ。野菜や果物を十分にとることも、がん予防につながる可能性が高い。総合ビタミン剤の摂取がこれらの代わりになるものではないことに注意してほしい」と付け加えている。Multivitamin Use Among Middle-Aged, Older Men Results in Modest Reduction in Cancer(ハーバード大学 2012年10月17日)(Terahata)◀ 前の記事

男性の更年期障害「LOH症候群」 男性ホルモン低下を改善- 日本生活習慣病予防協会 -
だ。 泌尿器科や男性更年期外来などの診療科では、男性ホルモンの測定やそれに関わる診療を行っている。LOH症候群の診断のためには、血液検査で男性ホルモンの値を調べたり、身体症状・精神症状・性機能症状などについて調べたりする問診などが行われる。生活を改善すればLOH症候群の進行を抑えられる LOH症候群の最大の要因は加齢だが、進行を予防するために、日常生活に気をつけて男性ホルモンが低下しないようにすることが重要だ。食事では、タンパク質の少ない食事を続けていると男性ホルモンが低下するので、野菜だけでなく肉や魚もしっかり摂取することが大切だ。 適度な運動も必要だ。ウォーキングなどの有酸素運動がテストステロン値を上昇させることが知られている。また、運動不足の人では内臓脂肪が蓄積されることが高く、それがテストステロン値を減らす原因になる。 また、長期間にわたって強いストレスを受け続けることも悪影響をもたらす。仕事や趣味で生きがいをみつけることは、男性ホルモンを増やす作用があり、ストレスを発散する効果も期待できる。 さらに、睡眠はテストステロンの分泌を維持するために極めて重要と考えられている。規則正しい生活を心がけて十分な睡眠をとることも大切だ。テストステロン値が低下した男性でうつ病リスクが上昇 米国のジョージ ワシントン大学医学部の研究グループが、テストステロン値が低下している男性ではうつ病のリスクが上昇するという研究を発表した。 研究グループは、血中のテストステロン値が200~350ng/mLの20~77歳の男性200人(平均年齢48歳)を対象に、テストステロン値の測定とアンケートによるうつ病の検査を行った。 その結果、参加者の56%でうつ病のスコアが高いことが判明した。うつ病に加え、意欲低下、性欲低下、勃起不全といった症状も多くみられた。 参加者の約4割は過体重や肥満で、ウォーキングなどの運動を習慣として行っている男性が少ないことも判明した。 過去の研究では、テストステロン値の低い男性は高い男性よりメタボリックシンドロームの発症リスクが約3倍高いと報告されている。 「肥満や運動不足といった生活スタイルを改善すれば、テストステロン値を改善できる可能性があります」と、研究者は指摘している。治療の基本は低下した男性ホルモンを増やすこと 医療機関で受けられるLOH症候群の治療の基本は、低下した男性ホルモンを増やすことだ。主な治療法としては、男性ホルモンであるテストステロンを注射で補充する方法、男性ホルモンをつくるよう脳からの指令を伝えるホルモンを注射で補充する方法などがある。 ホルモンの補充は半年から1年を目安に行われる。激しい副作用のおそれは少ないが、男性ホルモンは前立腺がんの細胞を増殖させるので、前立腺がんのリスクのある男性や前立腺肥大症のある男性はこの治療を受けることはできない。 LOH症候群の症状がみられる場合でもテストステロン値がそれほど低くない場合がある。そうした場合は、ホルモン補充療法ではなく、漢方薬により症状の改善をはかる場合